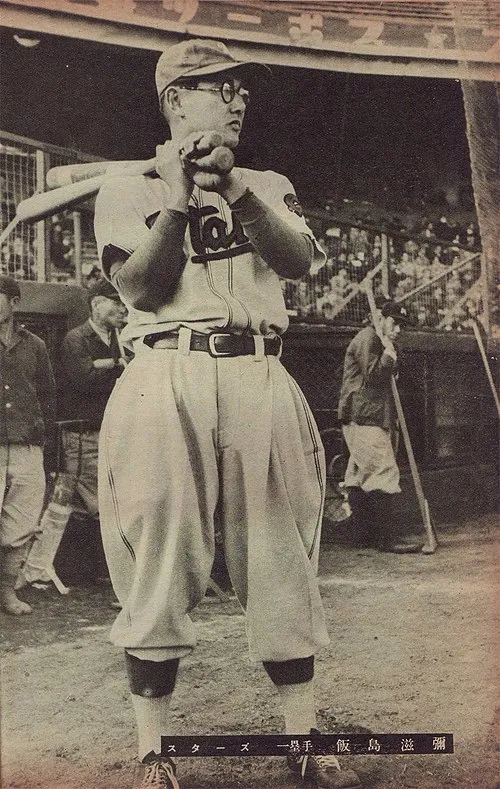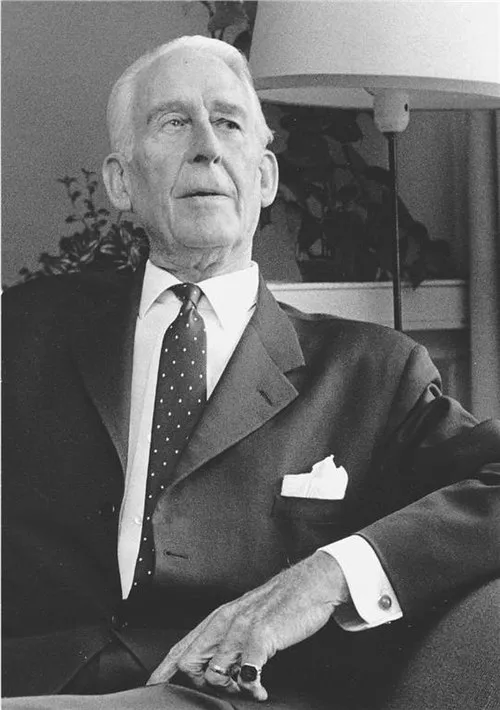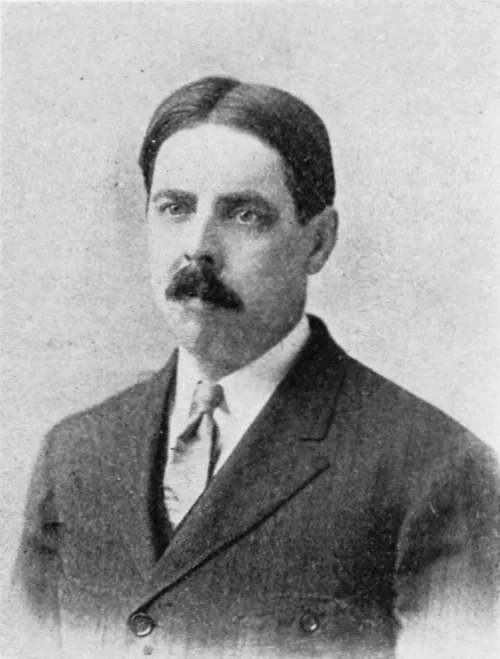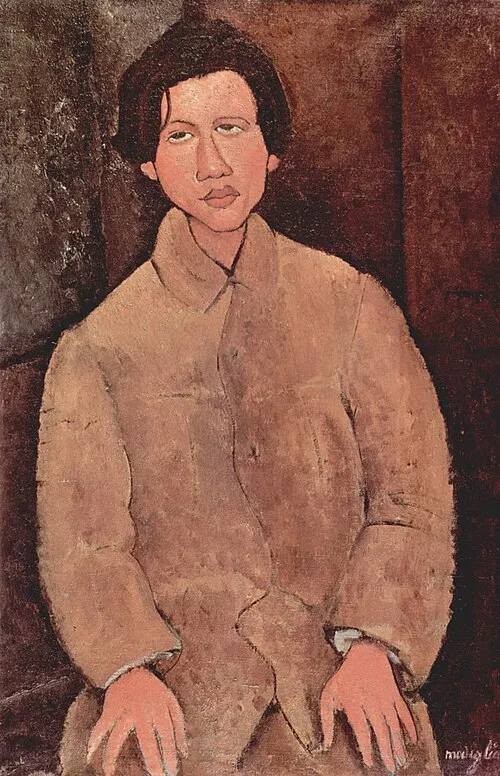名前: ドミートリイ・ショスタコーヴィチ
職業: 作曲家
生年: 1906年
没年: 1975年
国籍: ロシア
代表作: 交響曲、弦楽四重奏曲
年 ドミートリイ・ショスタコーヴィチ作曲家 年
音楽の世界において彼の名前は決して忘れ去られることはないその名はドミートリイ・ショスタコーヴィチ年ロシアのサンクトペテルブルクで生まれた彼は幼少期から音楽に親しみその才能を開花させていったしかし彼の人生は決して平坦ではなかった特にソビエト連邦という政治体制下で育ったことで彼は数多くの困難や試練に直面することとなる
ショスタコーヴィチが音楽家として成長する過程には多くの影響を与える出来事があった若き日の彼は年にレニングラード現在のサンクトペテルブルク音楽院に入学しそこで作曲家としての基礎を学んだしかしそれにもかかわらずこの時期のロシア革命による社会的混乱や不安定な政治状況が彼自身とその作品に強い影響を及ぼすことになる
年代初頭ショスタコーヴィチはようやく名声を得始めた交響曲第番は特に高い評価を受けそれによって若き天才作曲家として一躍注目される存在となったしかしその後すぐに待ち受けていた運命には厳しいものがあったそれにもかかわらずこの作品がもたらした成功は一時的なものでしかなかった
年ムツェンスク郡のマクベス夫人というオペラが大失敗しその結果ショスタコーヴィチはソビエト当局から非難されたこの非難は非常に厳しく人民芸術家として認められていたにもかかわらず一瞬で追放者へと変わり果てた皮肉なことに自身の日描いていた音楽とは裏腹に政府から批判されたことで生じた恐怖感が常につきまとっていた
それでもなおショスタコーヴィチは創作活動を続けた交響曲第番はその最も顕著な成果と言えるこの作品では政権への屈従を示したと言われながらもその背後には深い反抗心と苦悩が隠されているとの指摘もあるそれにもかかわらずこの交響曲のおかげで再び公然と活動できるようになり大衆から称賛される日が戻ってきたしかし本当に心から喜んでいたのであろうか
また重要なのは人間性として持つ複雑さだ大衆への配慮や政権への忖度とは裏腹に自身内心では苦悩し続けていたと思われるこの苦悩こそが多くの作品へと繋がり交響曲第番の制作へとも影響したこれはレニングラードと名付けられ多くの場合戦争について語り継がれる作品となっているその中でも人間ドラマや痛み生存欲求など複雑極まりない感情表現を見ることができおそらくこれこそ真実なのだろう
第二次世界大戦中という激動期には多くの国民と共鳴するような作品を書き上げ大衆との絆を確立していったしかし皮肉なことにその人気ゆえ権力者との関係構築もしなくてはいけなくなる再び不安定さとの闘争だったと言えるそしてこの関係構築こそ人生最大級とも言えるジレンマだった
戦後になると新しい時代背景下でショスタコーヴィチはいっそう多彩な表現方法を模索していく弦楽四重奏シリーズなど実験的試みも行いつつ新しい形態やジャンルへの挑戦を怠ることなく続けたしかしそれにも関わらず公私ともどもの不安定さから解放される日は訪れないままだったもちろん世間一般には高名になっていたものの自身だけには満足感とはほど遠かったと言われている
年月日この日ドミートリイ・ショスタコーヴィチという偉大なる作曲家はいまだ静寂無き世界へ旅立つその死去以降数十年経ち今日でもなお多岐にわたり影響力ある存在として知られている一方で不運にもソビエト連邦崩壊まで見届けぬまま地上界から去ったその遺産について語ればそれこそ新旧世代問わず聖域化され続けている
現在進行形で見ても尚彼女また彼達による演奏会場では多様性豊かな表現法フィルハーモニーオーケストラなど各所より演奏頻度高め展示され続けその意味合いや背景まで掘り下げ紹介され耳目集め通う事象を見る機会増えているまた同時代ながら普遍性溢れるメッセージ性持つという点でも賞賛さておりどんな困難にも耐え抜こうという思考法伝えて止まない姿勢自体おおよそ永遠不滅とも言えそう歴史的役割果たした故人だだけあれば今こうして再評価繰返す意味合いや重責感自覚否応なく感じざる負えない