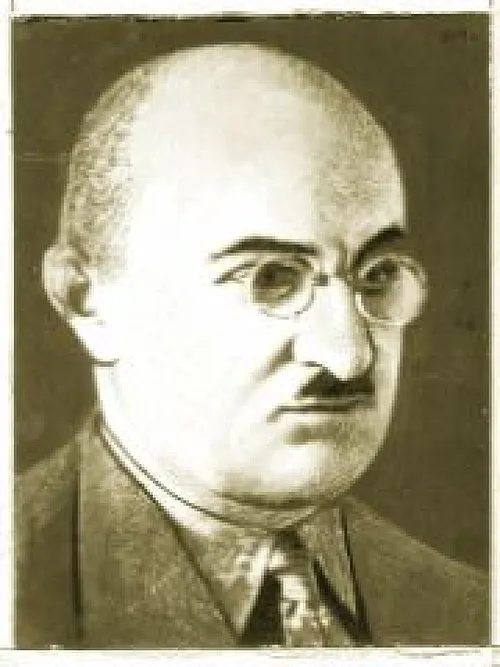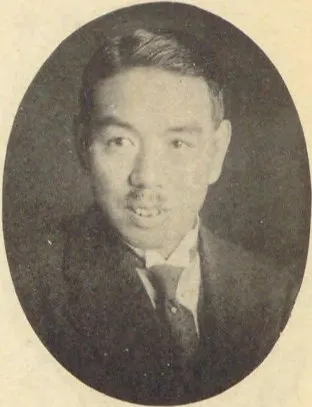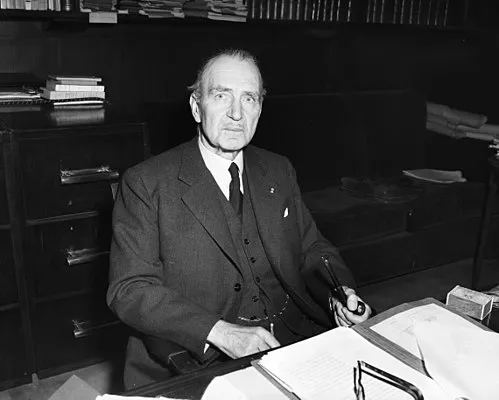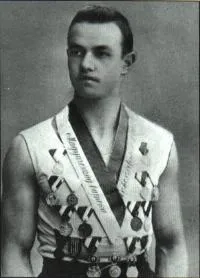生年: 1887年
職業: 落語家
名前: 三遊亭圓吉
没年: 不詳
三遊亭圓吉 落語家の名手
年東京の下町で生まれた三遊亭圓吉は日本の伝統芸能である落語界においてその名を轟かせることになる彼は幼少期から笑いを愛し友人たちと共に街角で物真似や小話を披露して楽しむ日を送っていたしかしその才能が世に知られることとなったのは彼がまだ十代半ばの頃だった
彼が初めて舞台に立ったのは歳の時新宿区内の小さな寄席で緊張しながらも自分自身を表現した観客から寄せられた温かい拍手は圓吉にとって忘れられない瞬間となったそれにもかかわらず初舞台後も数年は苦しい時期が続いた若き日の彼は多くの先輩方と同様に厳しい修行の日を過ごす必要があったからだ
それでも彼にはひとつ大きな強みがあったそれは生まれ持った独特なユーモアセンスと人との深い心のつながりだったこの才能のおかげで徐に名前が知られるようになり若干歳という若さで一座を持つことになった
成功への道
順調にキャリアを築いていた圓吉だがこの成功には多くの試練も伴っていた例えば自身の演目選びについて悩む日それまで流行していたものとは異なる新しいスタイルやテーマへの挑戦しかしその革新性こそが人から高く評価される要因となっていく
ある日彼はいわゆる現代落語と呼ばれるスタイルに挑戦することを決意したその結果多くの場合お茶漬けや餃子など日常生活との関連性ある話題へと発展したこの試みには賛否両論あったもののおそらくこれこそが彼自身を際立たせる要因だったと言えるだろう
困難な時代
年日本全体が戦争によって揺れている中でも圓吉は落語家として活動していたしかしそれにもかかわらず経済的には厳しい状況だったこの時期多くのお客様がお金よりも生活必需品へとシフトしてしまい寄席への来場者数も激減してしまう
皮肉なことにこのような困難な状況下でも演芸という文化は重要視されたそのため仲間たちとの絆や支え合うことで苦境を乗り越えて行こうとも努力した果たしてこの期間中にも新しいネタや演出法へ積極的に取り組むことで更なる飛躍につながる道筋を見出すこととなる
文化への貢献
三遊亭圓吉による貢献は単なる芸人としてだけではない文化人として日本社会全体への影響力も無視できない存在だったと言える他ジャンルとのコラボレーション企画や新進気鋭な作家との対談など様な活動で知られているこのような活動によって多様性ある日本文化へ向けた架け橋とも言える存在になっていったまた笑いを通じて国民全体へ元気づける役割も果たしたのである
遺産と思索
しかし彼には一つ大きな欠点もあったそれこそ人間関係について深刻化しすぎてしまう傾向だろう当時有名無名問わず多くのお弟子さんや仲間達と共演する機会も多かったためそれぞれとの関係構築には細心注意を払わねばならず逆説的にもその関係性ゆえ多忙すぎて本業がおざなりになる危険性まで伴ったのである
死後生き続ける笑い
おそらく今世紀末まで私達の日常生活でも引き継ぐべき価値観とも言われている満面の笑みと深いつぶやきを交えた会話の大切さそのようなお姿勢こそ百年以上経過した現在にもなお影響力持ち続けている証拠ではないだろうか歴史的背景から見ても興味深さ満載またその実績・作品群映像化され現在人気コンテンツ映画化等絶賛製作中等噂聞いてたりしますこれこそ新世代インフルエンサー(注:没年不詳)