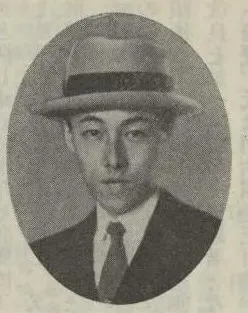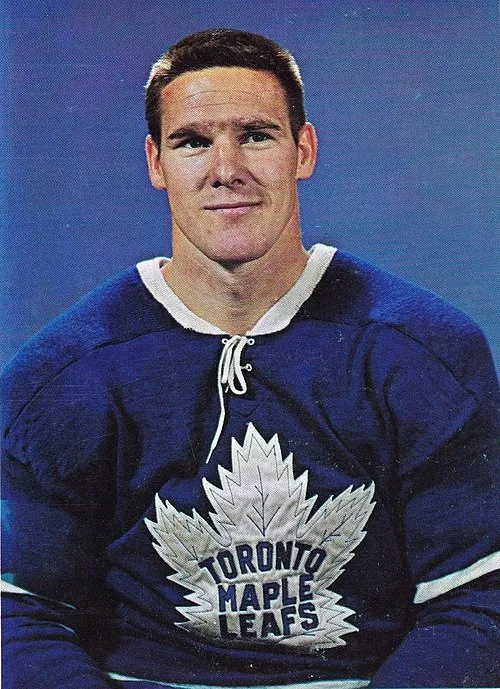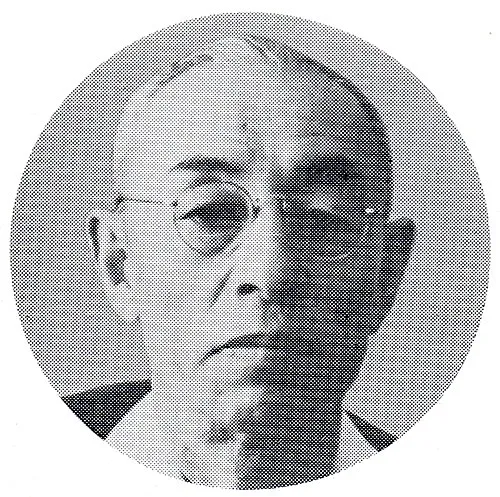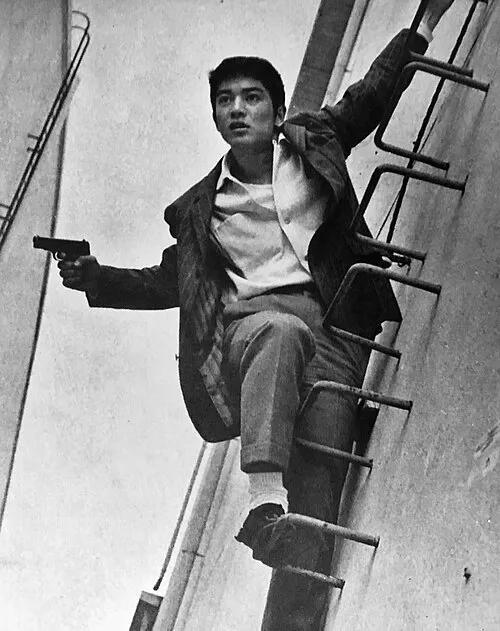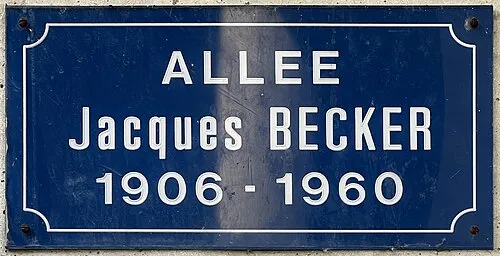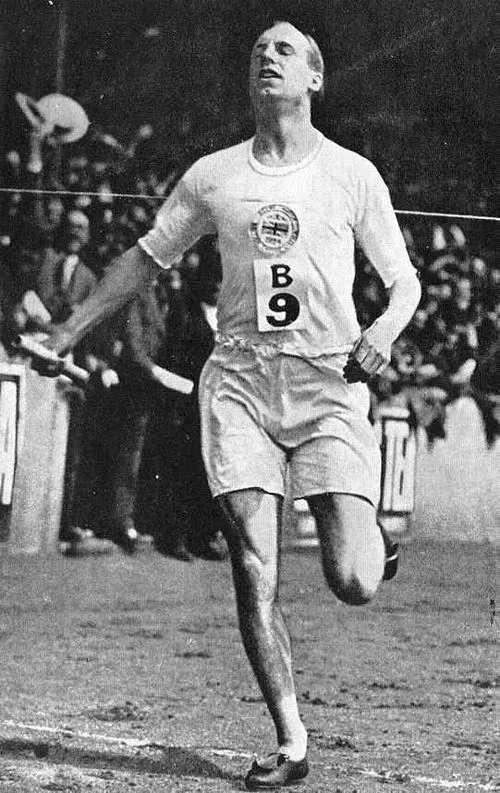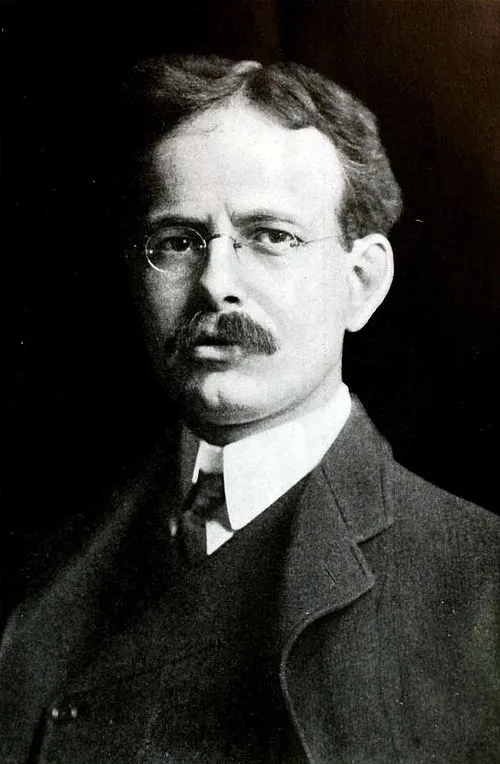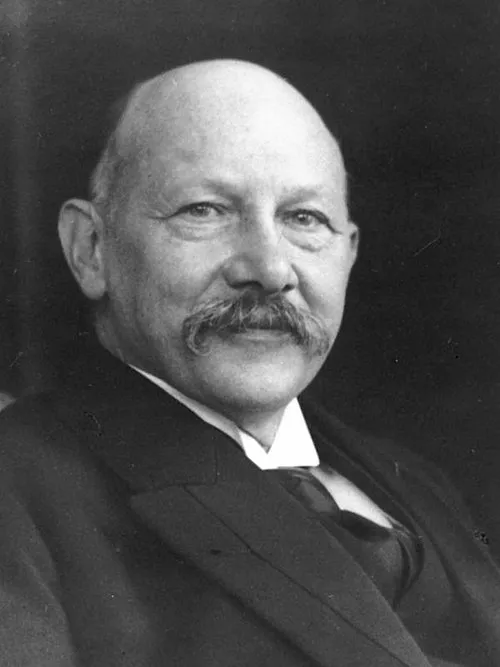名前: ミハイル・ショーロホフ
生年月日: 1905年
没年: 1984年
職業: 小説家
国籍: ロシア
主な著作: 『静かなるドン』
年 ミハイル・ショーロホフ小説家 年
ミハイル・ショーロホフの物語
年ロシアのドン川沿いに小さな村で生まれたミハイル・ショーロホフ彼は貧しい農民の家に育ち幼少期から大自然と農民文化に親しんだそのため彼の作品にはロシア南部の風景や人が色濃く描かれているしかしこの素朴な環境が後に彼を作家として形作ることになるとは当時誰も予想していなかった
若き日のショーロホフは第一次世界大戦に従軍しその体験は彼の感受性を一層豊かにしたしかしそれにもかかわらず戦争から帰国した後彼は地元の社会主義運動に参加する道を選んだそこで出会った仲間たちとの交流が彼の創造力を刺激することになりその結果として短編小説や詩を書き始めたこの初期作品群にはまだ未熟さが残っていたものの後の傑作への布石となったことは間違いない
年静かなドンを執筆し始めるとそれは文学界で注目を集める大作へと成長していったしかしこの壮大な叙事詩を書く過程では多くの苦悩と葛藤が伴った社会主義政権から求められる政治的メッセージとの板挟みに悩みつつもその中で描いた人間ドラマには真実味があったおそらくこの時期こそがショーロホフ自身が文学とは何かという問いを深く考えざるを得なかった瞬間だったと言えるだろう
静かなドンの成功
年静かなドンがついに出版されその反響は凄まじかったこの作品ではコサックたちの日常生活や愛情人間関係まで深く掘り下げて描写されており多くの読者から共感を呼び起こしたしかしながらこの成功にも皮肉な展開が待っていた当時ソ連政府から課せられた規制や検閲によって自身が表現したかったテーマやキャラクターについて自由度は制限されたそしてそれにも関わらずそうした逆境こそが逆に彼自身の文体へ新たな奥行きを与えたとも言える
受賞と評価
年代にはノーベル文学賞を受賞しその名声はいよいよ高まった静かなドンは映画化され多くの芸術家によって様な形で表現され続けているそれにもかかわらず一部では政権との妥協として否定的に捉えられることもありこのような評価には議論の余地もあるだろう一方でその作品自体は人間存在への深い理解と思慮ある視点を提供し続けている
晩年と遺産
晩年になるにつれショーロホフはいわゆる穏健派として知られるようになり多くの日常的問題について論じるようになった皮肉にもその穏和さゆえに一部では過去のおいて果敢だった若者像との乖離を指摘する声もあったしかしながら新しい世代への影響力や教訓という面では今なお重要視されているそして年には生誕周年という節目で再び注目された
今日まで続く影響
ショーロホフ亡き後もその影響力は衰えていない
静かなドン の物語性や人への洞察力は今日でも多くの作家やアーティストによってインスピレーションとして引き継がれているこの繋がりこそがおそらく最も価値ある遺産なのかもしれない例えば日本でも数多く翻訳版として親しまれており異なる文化圏でも共鳴している点などこれは言葉以上で伝わる普遍的テーマなのだろう
ちなみに静かなドンは年代まで様な演劇プロジェクトなどでも取り上げられており新しい解釈によって再発見され続けています このこと自体がおそらくミハイル・ショーロホフという人物とその創造力への終わり無き敬意とも取れるでしょう