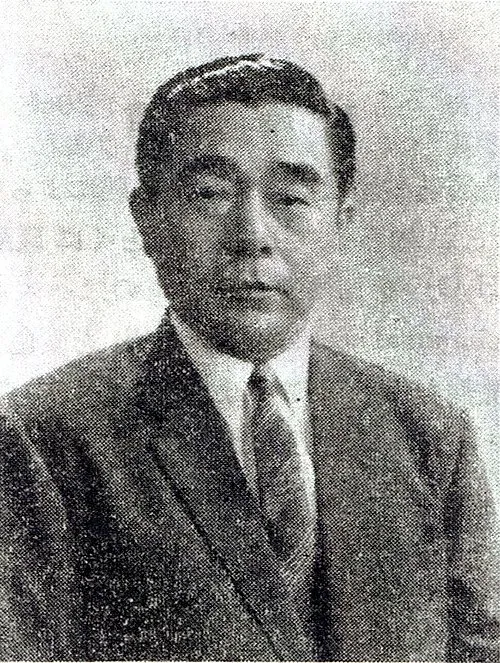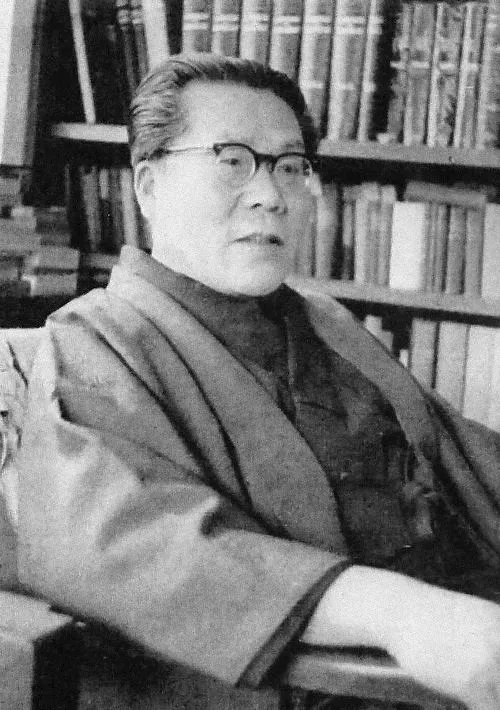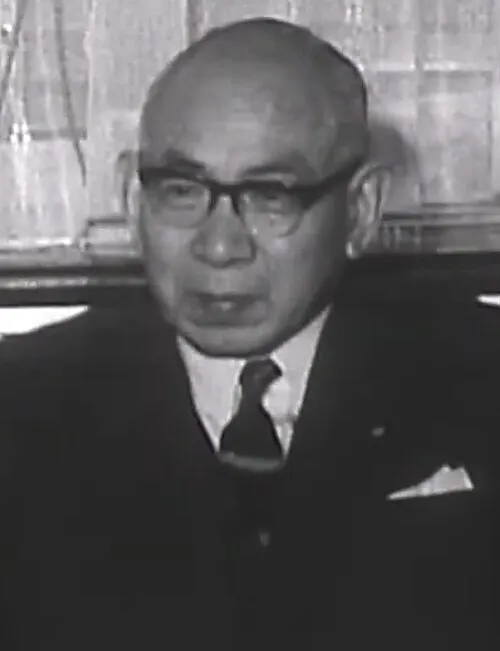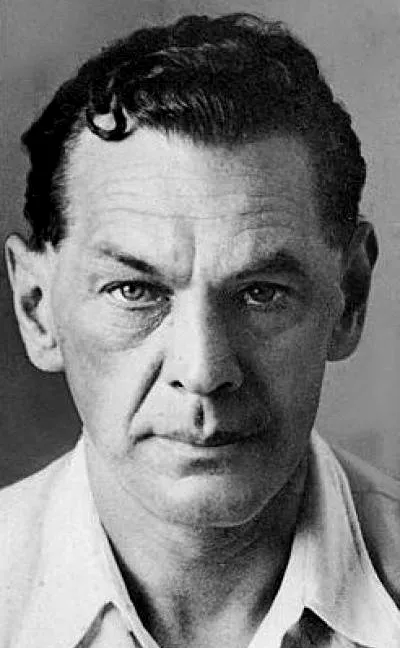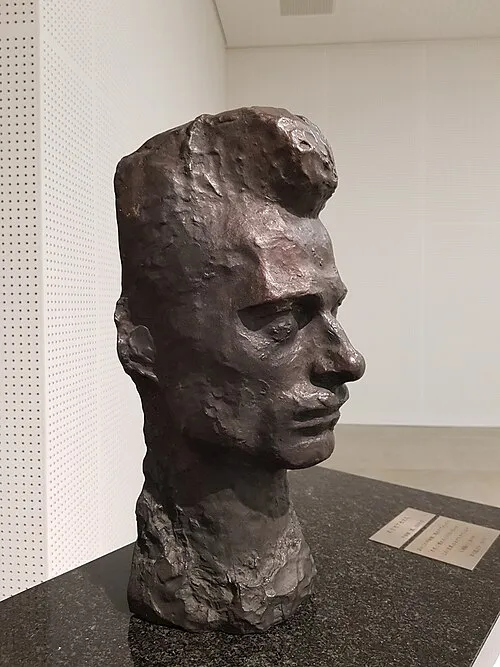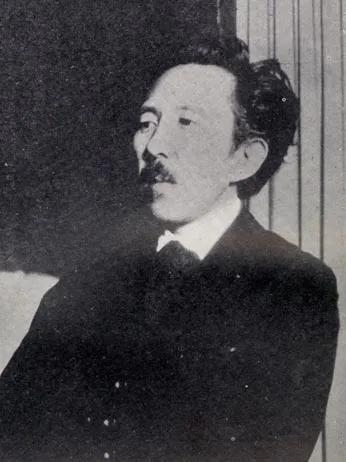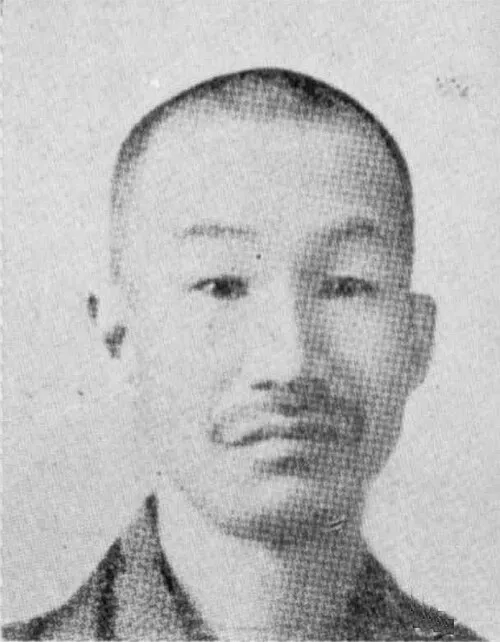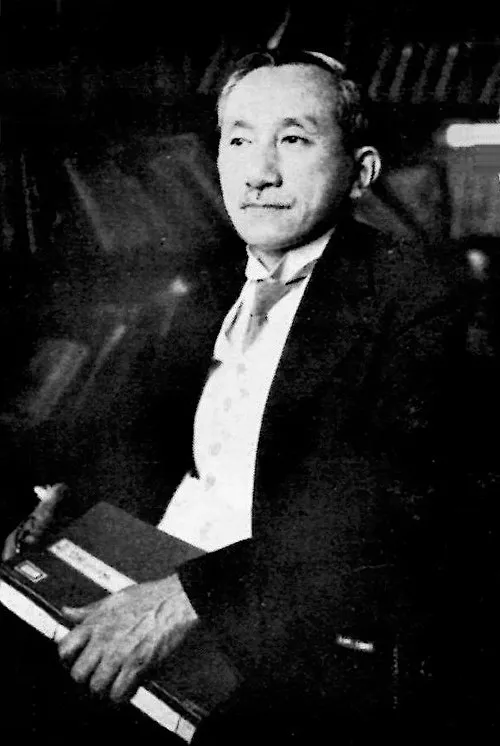名前: 三枝佐枝子
生年: 1920年
職業: 編集者、評論家
没年: 2023年
三枝佐枝子編集者と評論家の足跡
年穏やかな春の風が吹く中日本のある町に一人の女児が誕生した彼女の名は三枝佐枝子まるで運命を予感させるように彼女は後に日本文学界で欠かせない存在となる運命を背負って生まれてきたしかし彼女の人生は単なる偶然ではなく多くの選択と試練によって形作られていった
幼少期から文学に親しんだ彼女は高校時代にすでに詩を発表し始めていたそれにもかかわらず周囲の期待とは裏腹に大学進学を果たすことはなかったおそらく彼女自身が持つ独自の感性と自由な精神が影響していたと言えるだろうそして年代その情熱はさらに深まり小さな出版社で編集者として働き始めた
初めて手掛けた雑誌の記事には自身が抱いていた社会への疑問や文化への愛情が色濃く表現されていたそれでも編集者としての日は平坦ではなかった特に戦後日本社会は大きな変革期を迎え多様性や自由について語る声が高まっていたこの状況下で彼女は自らもその一翼を担うべく活動を広げていった
新たな挑戦と成功
年代には多くの文芸誌や評論集に寄稿するようになりその鋭い視点から成り立つ文章は次第に多くの読者から注目されるようになったしかしながらそれにもかかわらず一部から受ける批判も少なくなく女性作家という枠組みにはまることへの抵抗感もあったと言われている
年代になると三枝佐枝子はいよいよ編集長として名を馳せ始めたその時期には多くの新人作家との出会いやコラボレーションがありおそらくそれこそが彼女自身を刺激する原動力となったのであろうまた新しい才能を見出す目利きとして業界内外から評価されたことも皮肉だったかもしれない若手作家たちへの支援活動も行いそれによって新しい文学ムーブメントを形成していった
晩年まで続けた情熱
歳代になってもその情熱は衰えず多忙な日だったしかし年齢やキャリアという言葉では片付けられないほど人との対話や文化交流へ向けた姿勢こそが彼女自身だったそして歳という高齢になってなお新しい作品を書き続け自身の視点から過去と現在について鋭利な評論を書く姿勢には驚かされた人も多かっただろう
文化遺産として残したもの
年その長い旅路が終わりを迎えた際日本中には悲しみだけではなく感謝も広まった文学とは何かを問い続け自分自身のみならず周囲にも影響力を与え続けてきた三枝佐枝子その死後多数の記事や書籍で追悼されることとなり文壇母と称賛された一方で皮肉にも今なお現代日本社会でも議論される女性作家の立場について考える契機ともなっている
歴史的背景との関連性
実際日本国内外では女性著述家や批評家的存在が徐に認知されつつある中その流れへ大きく貢献した一人として位置づけられるだろう特定世代によるサポートだけではなく自身による開拓精神こそ重要だったと思われ次世代へのメッセージとして歴史的意義まで感じさせられることとなった
参考文献