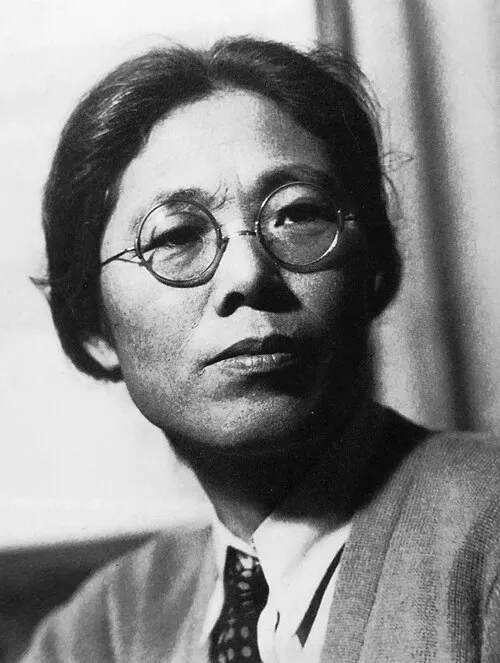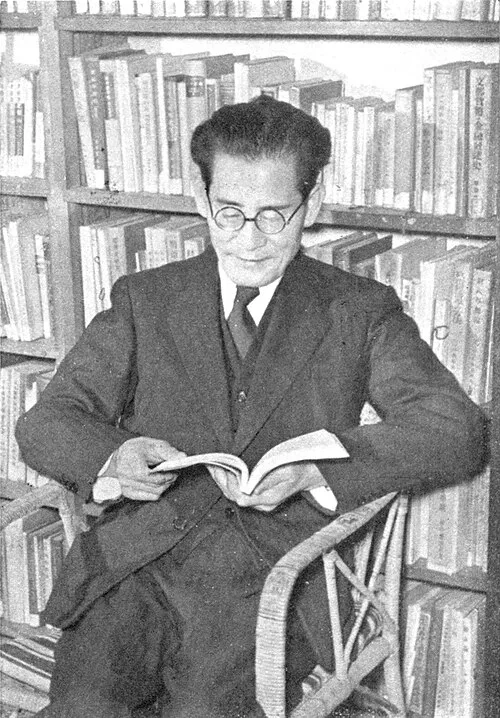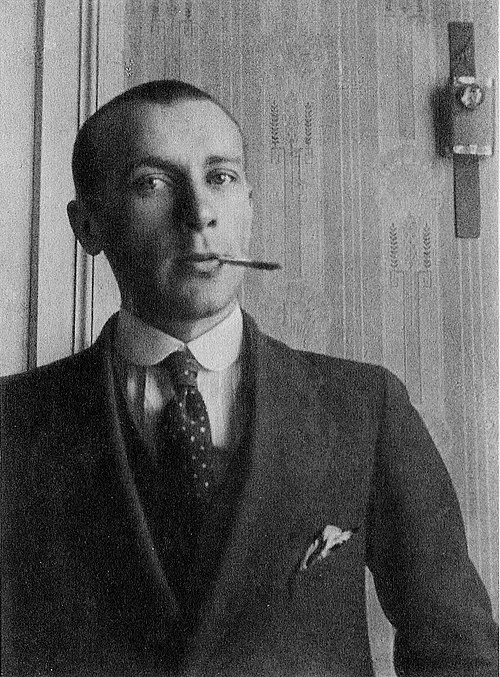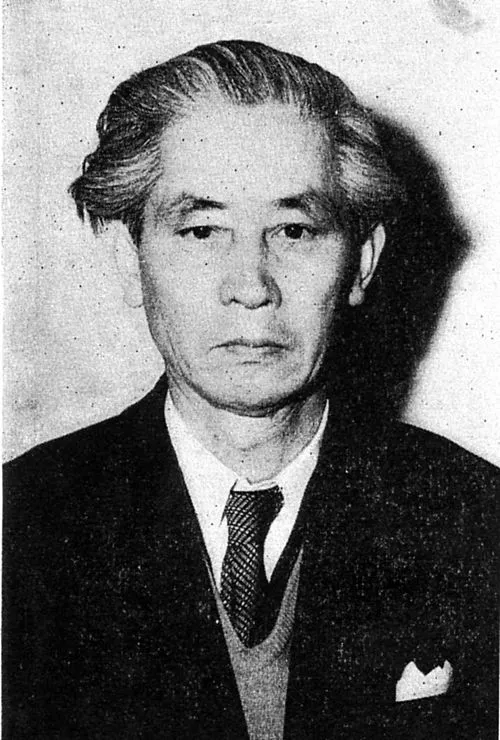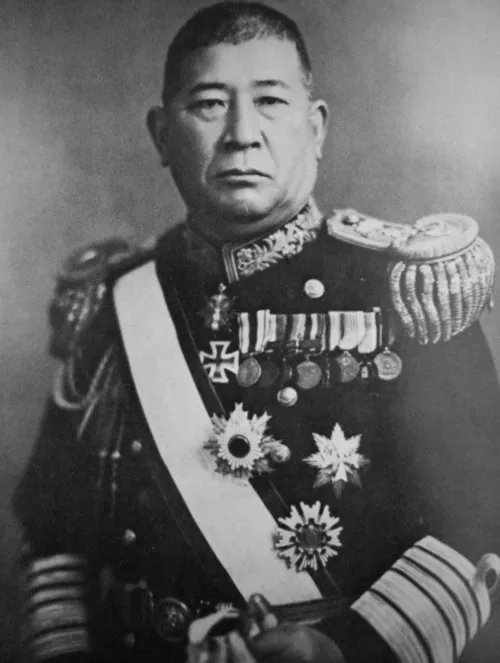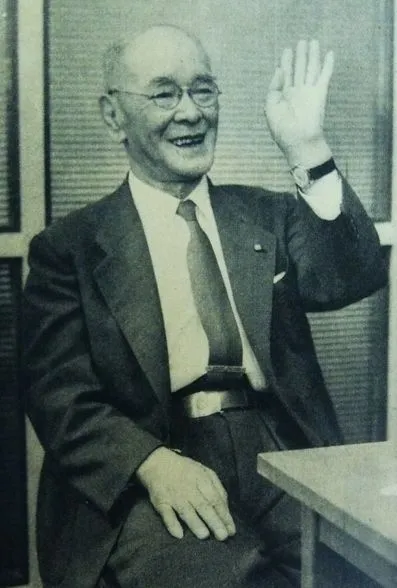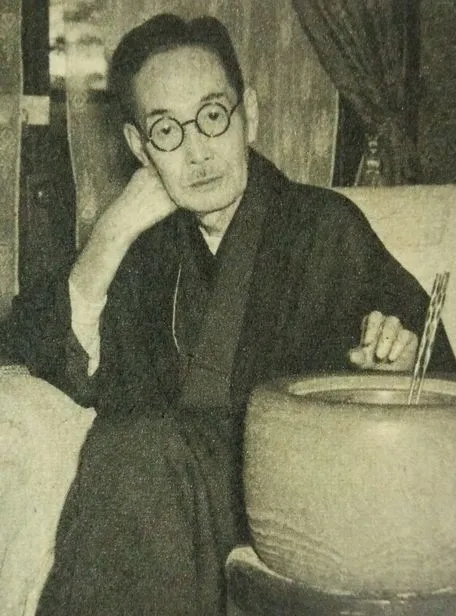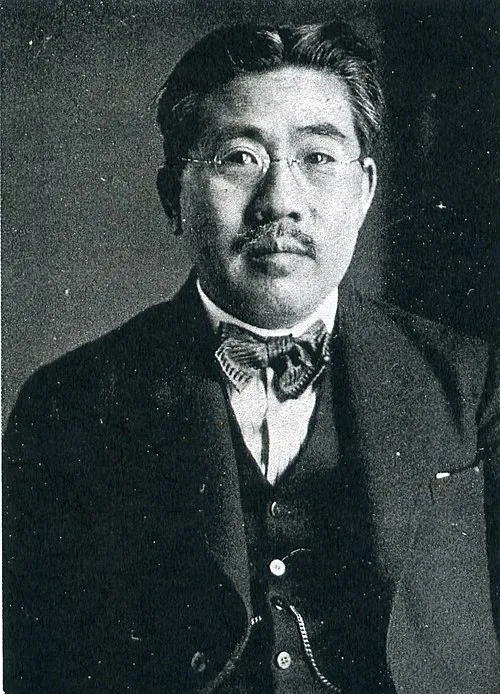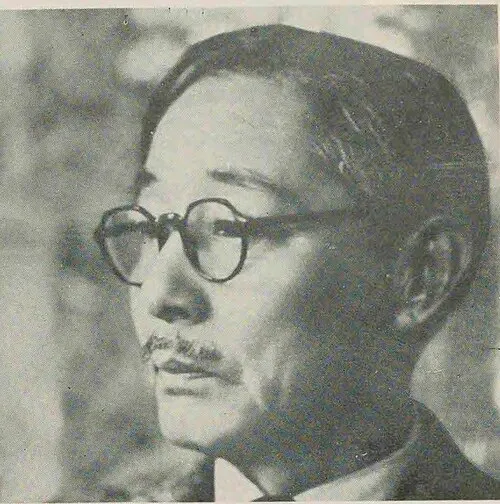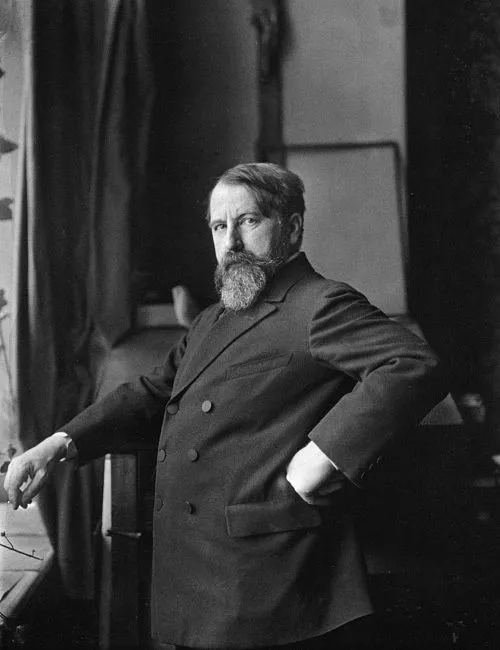生年月日: 1903年
名前: マリア・ライヘ
職業: 考古学者
死亡年: 1998年
年 マリア・ライヘ考古学者 年
マリア・ライヘは年の夏の日にペルーの小さな村で生を受けた彼女の誕生は一見すると普通の出来事に思えるかもしれないしかし彼女が後に成し遂げる業績を考えるとその瞬間は運命的だったと言える彼女は貧しい家庭に育ち父親が果樹農園を経営していたため自然と親しむ環境で育ったこの背景が後の彼女の研究に深い影響を与えることになるとは当時誰も想像できなかった若き日のマリアは学校教育への情熱を抱き特に数学や科学への興味が強かったそれにもかかわらず女性が学問の世界で成功することは難しい時代だったしかしそれにもかかわらず彼女は自らの道を切り開く決意を固めていた大学では医学や地質学など多岐にわたる科目を学びその知識が後に彼女の考古学者としてのキャリアにつながっていくことになるそれから数年後年代にはアメリカ合衆国とペルーとの関係改善が進みそれによって考古学的調査も活発化したこの流れに乗る形でマリア・ライヘも南米各地でフィールドワークを行う機会を得たしかし皮肉なことにこの時期には第二次世界大戦という大きな混乱もあったため多くの研究者たちはその影響で活動が制限されてしまったそれでもライヘは決して諦めず自身の興味あるテーマについてひたむきな探求心を持ち続けた特筆すべきなのはナスカの地上絵と呼ばれる巨大な図形群との出会いだおそらくこの瞬間こそが彼女の人生で最も重要な転機となったのであろう年代初頭西部ペルーへ向かう旅路で偶然ナスカ平原上空からこれらを見ることになりその壮大さと神秘性によって深い感銘を受けたその景色こそが長年追い求めていた人類史を解明する鍵になると確信したからだしかしながら多くの場合人から疑念や批判的視線にも直面した何故このような巨大図形を書いたり描いたりしたと思う単なる迷信なのではという声も少なくない中これは古代人による天文学的観測や宗教儀式とも関連していると主張し続けたのであるこのような思考過程から導かれる結論には多く議論される部分もあるもののおそらくそれこそが当時としては前衛的だったと言えそうだまた一つ忘れてはいけないエピソードとして西洋社会との葛藤も存在するライヘ自身多くの場合女性だからという理由だけで自身評価されない苦悩もしばしば味わっているそれにも関わらず自身と南米文化への愛情一体感ともいうべき思いから周囲との協調性や協力体制構築へ向け努力し続ける姿勢には多く人感銘受けただろうそして年代半ばまでには多様性豊かな文化背景持つ数十名以上研究者同士共同作業行われ新しい発見へ繋げてゆこうとしている現場展開された年代には多国籍企業など資金援助獲得することで本格的調査始まりこの動きを牽引した人物として名声高まったまた注目すべき点として個人的スタンス持ちながら透明性重視する姿勢示す努力みせただろう他方では経済支援受実施できる環境整備促進活動交渉行使すればより良好環境確保致しかねれば問題残念無駄となってしまう点認識有無共通意識醸成必要不可欠ではとも言えそうだ苦笑年には歳という長寿界隈獲得達成その余生全て変革期迎えたい心強さ映していた先達による道筋歩みつつ新世代発掘継承任務遂行下日本国内外へメッセージ広まってゆくだろう他者分野知識統合目指す意義理解志望拡充可能性示唆表明と思えますね今日でもナスカ平原上空から眺める際その壮麗さと神秘性によって多く観光客訪れる一方奇妙にも忘れ去られん歴史象徴表現物未解明謎連鎖未完結状態維持今なお遺族登場法典記述含む更なる探求繰返せ果たして何処未来示唆提供選択肢残されているそうこの奇跡的出会いや不屈精神こそ彼女引き寄せ方向付与周囲及び後世全体浸透効果注入可能だったでしょうねつまり文明興隆過程相互作用結果必然ですそして今尚周辺地域再評価基盤成立途絶不断挑戦事例収集展開実施中