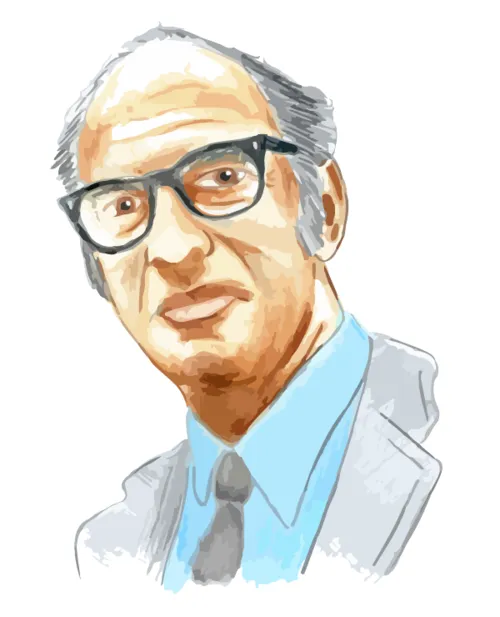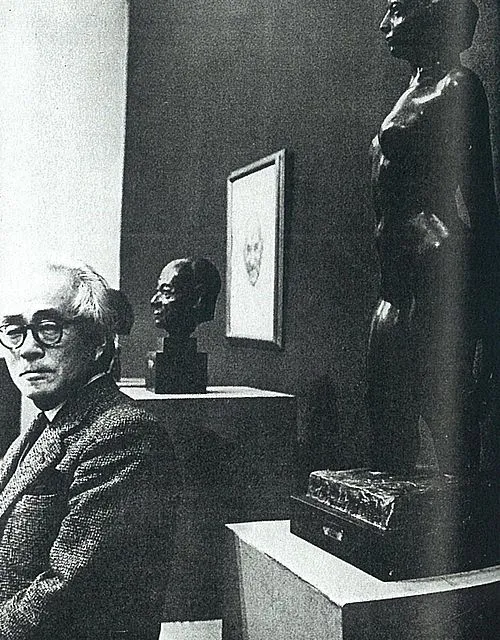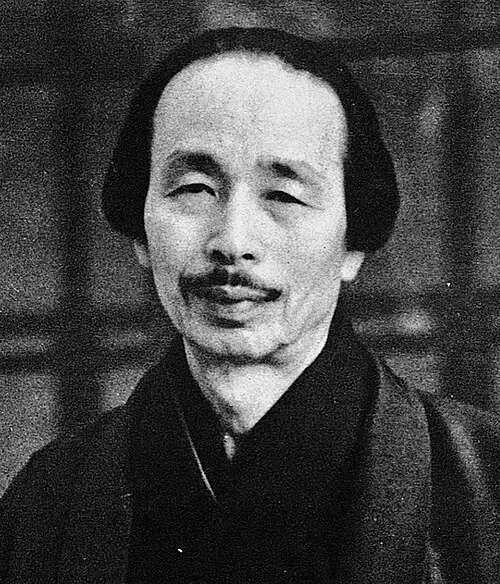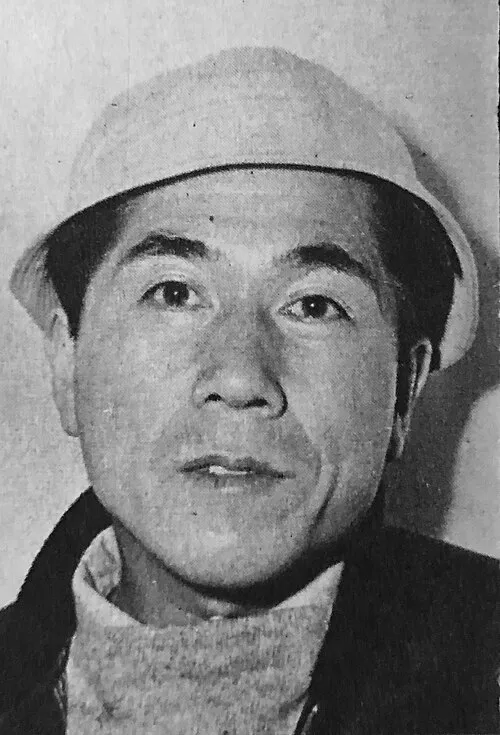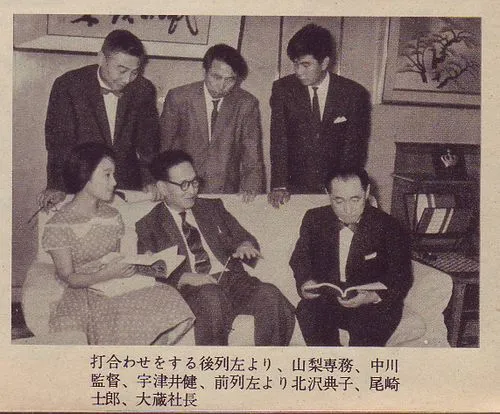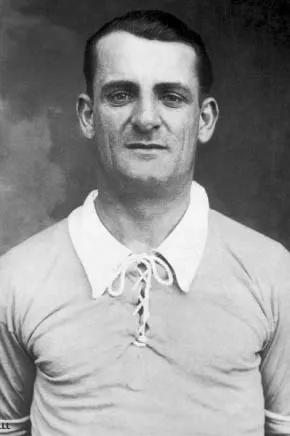名前: 北村昌士
職業: ミュージシャン、音楽評論家、編集者
生年: 1956年
活動開始年: 2006年
年 北村昌士ミュージシャン音楽評論家編集者 年
北村昌士は年に日本の静岡県で生まれた彼は音楽の世界においてその独自の視点と豊かな感受性で知られているしかし彼の人生は単なる音楽への愛情だけでは語り尽くせない若き日友人たちとともにジャズクラブを訪れることが多くそこで彼は音楽を感じるだけでなく自らも演奏することを夢見ていた
大学時代北村は文学と音楽を深く学びながら多様なジャンルに影響を受けていったそれにもかかわらず彼が特に心惹かれたのはロックやポップスだったこの時期おそらく彼の中で何かが芽生え始めた彼自身も言っていたように音楽は言葉よりも強力なコミュニケーション手段なのだと感じ始めたのだろう
卒業後北村は音楽評論家としてキャリアをスタートさせることになるしかしその道には困難も多かった初期のころ多くの記事を書いたものの評価されず辛酸を舐める日が続いたそれでもなおその情熱は冷めることなくむしろさらに燃え上がったと言える皮肉なことに最初の記事が掲載された際には自身ですら信じられない気持ちだったという
年代には日本国内外の様なアーティストとのインタビューやコンサートレビューを書く機会が増えていきその才能が次第に認められていったしかしそれにもかかわらずメディア界では競争が激化し新しい才能によってすぐさま忘れ去られる可能性もあったそのため北村はいかにして独自性を保つべきか苦慮したことであろう
年代初頭おそらくこの頃から彼自身の日記とも言えるエッセイ集や書籍への執筆活動も本格的になり始めたその作品群には日本社会や文化について鋭い洞察力と批判精神が表現されているこの過程で一部ファンから批評家としてだけでなく作家として評価されるようになっていったただしそのスタイルはいわゆる伝統的な批評とは一線を画し人間味溢れる視点から展開されていた
年代になると特に年以降テレビやラジオなどでも頻繁に姿を見るようになりその存在感はますます強まり多くのファンから親しまれるようになったしかしそれとは裏腹に自分自身について反省する機会も多かったという本当に大切なのは何なのだろうという問いへの答え探しそれこそ北村昌士の日常だったとも推測できる
一方でこの時期には若手アーティストとの交流も活発化したその中でも特筆すべきなのは新進気鋭なミュージシャンとのコラボレーションだったこの試みこそ北村ならではと言えるでしょう世代間交流という新しい形態こそ実現できたのであるそしてそれによって新しい価値観や音楽スタイルも生まれていったと言われているただしこの取り組みが成功した背景には慎重さと思慮深さそして情熱的な姿勢あってこその結果だろう
しかしそれにも関わらず一部から厳しい意見も寄せられ商業主義に流されたとの非難すら受けたりしたそれでもなお多角的視点から商業と芸術を見極めようとしていた姿勢には多くの賛同者がおり続けたそしてその意義ある試みにより日本全国各地へ足繁く通いつつ新しい風潮を起こそうとしていたのである
残念ながら年現在まで健康問題など個人的苦難にも直面しているものと思われます最近では等で彼の日常生活や思考過程について語り合う場面もしばしば目撃されており一部ファン達から温かな声援・励ましなど寄せ集まっていますそれゆえ時代の波にも乗り遅れることなく貪欲さだけではなく柔軟性について深掘りする必要性とは何だろうという問い掛けになるのでしょうね
最終的には こうした複雑さ故かおそらくこれまで築いてきたキャリアそのもの以上として今後どんなメッセージ伝えて行こうとも期待していますそして現在進行形だからこそ尚更応援する声高まり続けています