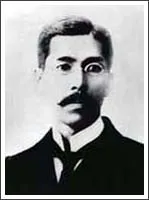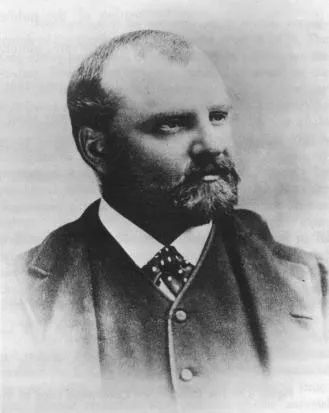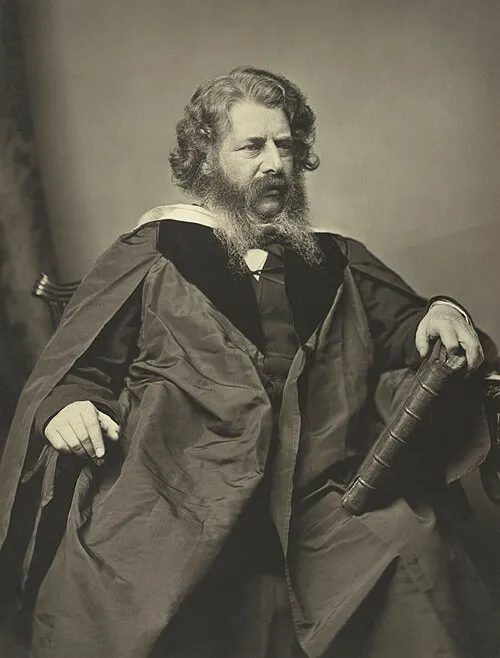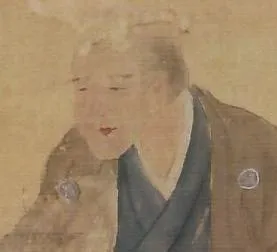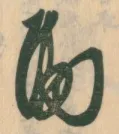名前: 3代目桂文枝
職業: 落語家
生年月日: 1864年
死亡年: 1910年
桂文枝 落語の巨星
年彼は江戸の町に生まれたまだ幼い頃から落語に興味を示していたというしかし彼の家族は伝統的な商人であり落語家になる道は決して平坦ではなかった何度も両親に反対されながらも彼は自分の夢を諦めることなく小さな寄席で修行を始めたのである
若いころ彼は先輩たちから厳しい指導を受けながら一歩一歩着実に成長していったそしてついに自身の芸名桂文枝を名乗ることになったこの名前には文という文字が含まれておりおそらく文学や物語への愛情が込められているのだろう
しかしその道のりは容易ではなかった初めて大きな舞台に立った時緊張と恐怖で心臓がバクバクしていたと伝えられているそれにもかかわらず大勢の観客を前にし自身の持ち味である巧妙な話術とユーモアで場を盛り上げることができたその瞬間彼は観客との絆を感じ取りそれが彼自身のスタイルとなっていった
そして年代には急速に人気が高まり多くの人から支持されるようになるしかし皮肉なことにこの成功は同時に多くの嫉妬や敵意も生んだ同業者から冷ややかな目で見られることもしばしばあったと言われているそれにもかかわらず不屈の精神で挑戦し続けたことでさらなる成功へとつながっていく
年代には日本中でその名が知られるようになり落語界三代目として君臨するまでとなった演じる内容も幅広く新作落語や古典落語など多彩なスタイルを披露したことで多くのお客様を魅了したこの変化こそがおそらく桂文枝という人物最大の魅力だったとも言えるだろう
新しい風 落語界への影響
桂文枝が築いた独自スタイルとは何だったかそれはただ単純なお話ではなく人の日常生活や社会情勢を巧みに取り入れた内容だったそのため多くのお客様が共感し一緒に笑うことができたのであるまた三代目と称されるだけあってその存在感とカリスマ性には誰も逆らえないものがあったとも言える
年代にはテレビ出演も果たすようになり一気にその名声は全国区へ広まったしかしそれでもなお舞台への思い入れは強かったテレビよりもライブパフォーマンスこそ本当の落語だという信念を持ち続けそれによって多くのお客様との絆を深めていたと言われているこの姿勢こそ本物として称賛された理由でもあると思う
晩年と遺産
代目桂文枝はその後年代まで活躍するものの高齢による体調不良から徐に公演数が減少していったそして年日本中がお祝いムード一色となって迎えたその誕生日直前皮肉にもその日記帳には最期の日を書き記す運命しか待ってはいなかった
文化的影響
教訓信念と思いやり
私自身自分のみならず他者への思いやりこそ大切なのです 桂文枝最後までその情熱と芸術心を持ち続け生涯現役だった桂文枝その死後から今なおその残した笑顔と共鳴する声笑う門には福来るという言葉通り多世代へ引き継ぐ形になっていますそして年現在多様化するエンターテインメント業界でも新世代によるオマージュ企画など見かけますそれゆえ彼自身だけではなく日本文化全体への遺産とも言えるでしょう