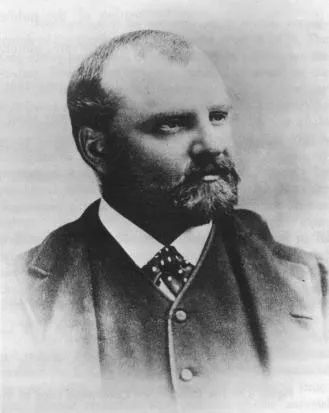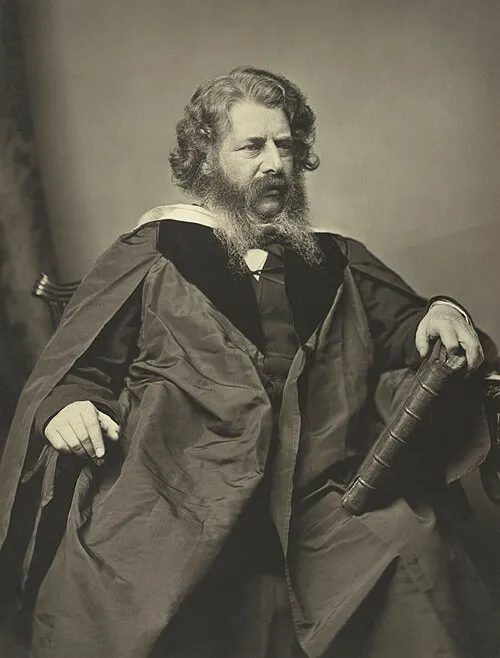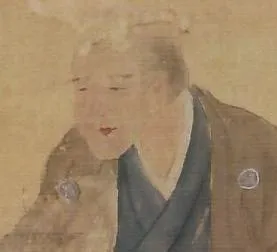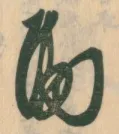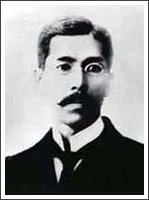
高山樗牛
国籍: 日本
死亡日: 1902年12月24日
年 高山樗牛文芸評論家 年
年日本の文壇における重要な人物高山樗牛がその存在感を示した彼は年に生まれ早くから文芸評論家としての道を歩み始めたしかしその道のりは平坦ではなかった若い頃から文学に魅了され自らの思想を形にすることに情熱を注いだものの時には孤独感や不安と戦うこともあった
高山は特に明治時代の日本文学における新しい風潮を感じ取りそれを批評することによって多くの作家たちへ影響を与えた彼が注目した作品には夏目漱石や島崎藤村といった巨匠たちが含まれていたそれにもかかわらず高山自身も常に変化し続ける文学界でどう自分を確立していくかという葛藤があった
それでも高山樗牛は自らのスタイルを模索し続けたそして年代には文芸評論という新しいジャンルで頭角を現し多くの読者から支持されるようになったこの時期彼は新しい日本文学への期待と共鳴する声となりその意見や視点が広く受け入れられるようになっていた
皮肉なことに彼自身が持つ批評眼は多くの場合他者との対立や誤解につながることもあったしかしその中で彼は自己表現としての批評活動に徹し多様な作家との交流や対話によって自らの思想も深まっていったと言える
高山樗牛の日は繁忙そのものでありおそらく彼には静かな時間など存在しなかった毎日のように本を書き新しい作品について考え続けた結果数多くの記事やエッセイを書き残したその中には本音とも取れる辛辣なコメントや鋭い分析も含まれておりそれゆえ周囲から賛否両論が巻き起こることもしばしばだった
またこの時期日本国内では近代化が進む一方で伝統文化への回帰も求められていた高山樗牛自身この二つの流れについて悩んだと言われている新しいものと古いものの狭間で揺れ動きながら人へどんなメッセージを届けるべきか常に考えていたのである
そして年高山樗牛はいよいよ一つ大きな舞台へと足を踏み入れるこの年彼はさらに広範囲な読者層へ向けて自分自身と作品への理解促進という使命感から講演活動にも力を入れるようになるしかしその活動には緊張感が伴うこととなり自身でも計り知れないプレッシャーとなっていたことでしょう
果たしてこの決断こそが高山樗牛の日を書物として世間一般へ普及させるためだったとも言えるただ一方で公演後には常なる批判的評価によって心労にも苛まれてしまうそれにも関わらずこの経験こそが後世への贈り物とも言える幅広い視野と深みある分析力につながっているのである
その後数年間高山樗牛はいろんな困難と向き合いつつ精力的な執筆活動を継続したそれにも関わらず一部ファンから見れば彼自身すべて望んだ通りになったわけではなく果たしてこの道選択こそ正しかったという疑問すら残された可能性もある
また高山樗牛の死去以降日本文学界には何人もの傑出した作家達太宰治や川端康成などが登場するしかし高山が残した数の記事・論文群によって今日でも議論され新旧問わず名作として称賛され続いているその著書群について今なお研究・検証されている姿を見る限り未だ多大なる影響力がありますね
今日でも情熱的批評というフレーズから思われる印象より強烈さ感じますそれゆえ現代社会とは裏腹となっていますただこれは私だけではなく多く人間味溢れる作品等あり触発された気持ちそれ故再評価につながっています他方で推測できますがおそらく当人自身無邪気だった面白さ含め反映された部分それぞれ考慮され判断していますね
こうして振り返れば高山という名まで令和時代でも色濃く響いています年現在多様性豊かな文化背景持ちながらも実際我持つ側面潜在的要素相互作用して形成されております