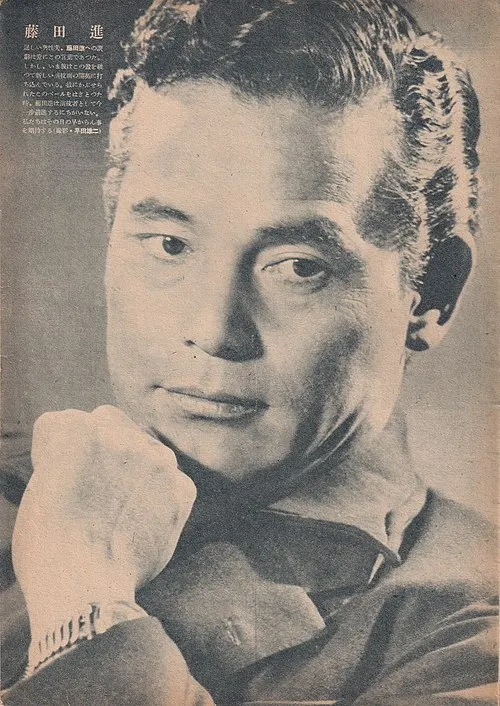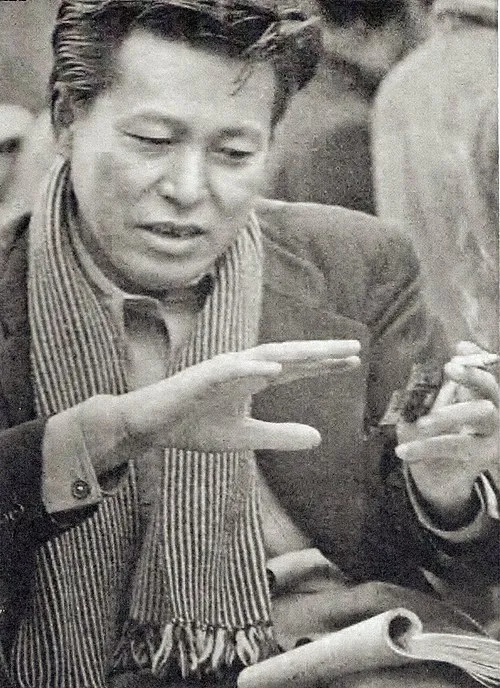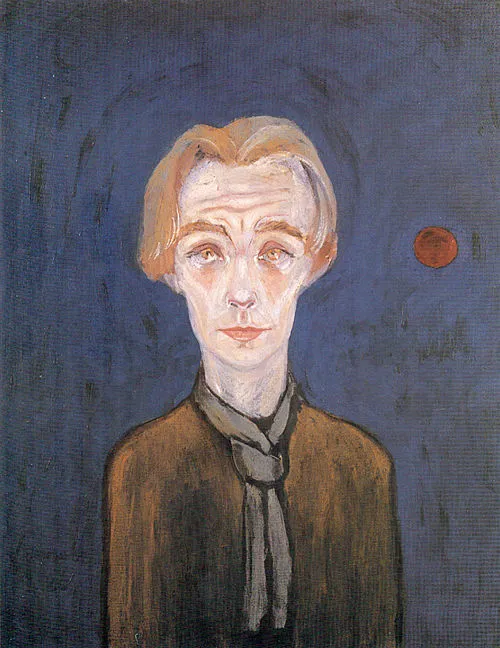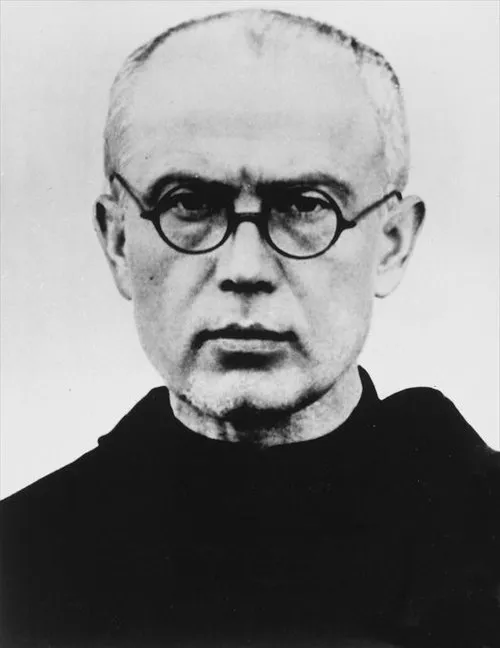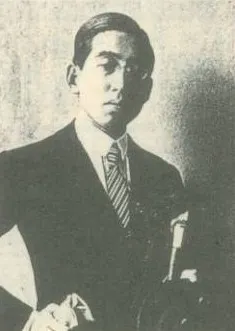名前: ジョセフ・ワイゼンバウム
生年月日: 1923年
職業: 計算機科学研究者
死去年: 2008年
年 ジョセフ・ワイゼンバウム計算機科学研究者 年
年ドイツのベルリンで生まれたジョセフ・ワイゼンバウムは後に計算機科学の分野で革命をもたらす存在となる彼の幼少期は当時のヨーロッパが抱えていた様な社会的・政治的混乱の影響を受けておりその経験が彼の人生観や職業選択に多大な影響を与えることになる
年代初頭第二次世界大戦が激化する中でワイゼンバウムは米国に移住することを決断したこの移住は彼にとって新しい希望と可能性をもたらすことになったしかしそれにもかかわらず新天地で直面した困難や葛藤もあった言語や文化の違いに苦しみながらも彼は精神的な成長とともに多くの知識と技術を身につけていった
大学では工学や数学を学びながらコンピュータプログラミングへの興味が芽生えていく年代にはこの新しい技術分野で重要な地位を確立し始める彼がおそらく最も知られている成果プログラムは年に発表されこの作品によって人間と機械との対話という全く新しい概念が広まった
は特定のキーワードに基づいて質問を投げかけ人間との会話が可能だと思わせるチャットボットだったしかし皮肉なことにその成功にも関わらずワイゼンバウム自身はこの技術が持つ倫理的問題について深刻な懸念を抱いていたこのプログラムによって多くの人が機械との対話から感情的なつながりを感じるようになる一方その真実性について疑問視されるようになったのである
その後彼はコンピュータ科学だけではなく人間中心設計や人工知能についても考察するようになり自身の哲学と信念について公然と発言する姿勢を見せた特にには限界があると主張し続けたことで多くの支持者から敬意を表され一方で批判者から反発も受けたしかしそれこそが彼自身の日常生活や研究活動への真摯さとも言えるだろう
年には という著書を書き上げ人間性とは何かという問いかけへ挑んだこの本では自動化された世界で人間として生き延びるためには何が必要なのかそれによって私たち自身が何者なのかという疑問へ深く迫っているその結果として人間性を重視したテクノロジー利用へのアプローチが提唱された
しかしその後数十年間テクノロジー業界ではブラックボックス化が進行し人はますます機械との関係性から疎外されてしまうそれでもなおワイゼンバウムは自らの日研究だけではなく公演や講義など幅広い活動によってメッセージを伝え続け自身の哲学的思考法への共感者との交流も絶えなかった
年多大なる業績と影響力ゆえその名声高きこの人物は歳という齢でこの世を去ったしかしそれまで築いてきたアイデアや価値観はいまだ多く語り継がれている今日でもワイゼンバウム氏による警告私たち人類自身がお互いどう向き合うべきなのかという問い掛け は新興テクノロジー社会でも色褪せない重要性となっているそれにも関わらず我現代人は相変わらず便利さばかり求め本当に大切なものから目を背けてしまう傾向があります