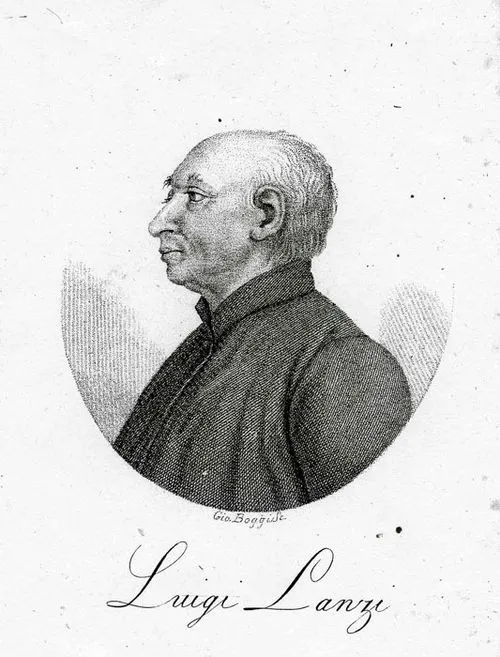生誕年: 1811年
名前: ハリエット・ビーチャー・ストウ
職業: 作家
死亡年: 1896年
年 ハリエット・ビーチャー・ストウ作家 年
ハリエット・ビーチャー・ストウ人間の尊厳を賭けた言葉の力
年アメリカのコネチカット州にある小さな町で彼女は誕生した家族は宗教的な背景を持ち特に父親は教育者として名を馳せていたしかし彼女が育つ環境には一方で強い信念ともう一方で当時の社会が抱える矛盾があった若き日のハリエットは周囲から受け取る影響を感じながらも自身の道を見出していくこととなる
彼女の文学への情熱が芽生えたのは思春期を迎えた頃だったその後すぐに多くの作品を書き始めるしかしそれにもかかわらず彼女が直面した最大の試練は奴隷制度という残酷な現実だったおそらく彼女はこの現実から目を背けることなくその苦しみや不正義に向き合う決意を固めていた
年結婚したハリエットは自身の家庭生活と作家活動を両立させながら多くの記事や短編小説を書くようになったそして年にはその後最も有名になる作品アンクル・トムの小屋を書くために準備することとなるこの作品では奴隷制度について赤裸に描写し人にその非道さと人間性への理解を促そうと試みたしかしこの挑戦的な行動は一部から強い反発も招いた
アンクル・トムの小屋が出版されるや否や大ヒットとなり瞬く間に広まっていったそれにもかかわらずこの成功には皮肉な側面も存在していた南部諸州ではこの本が焚書され多くの場合作者本人へも攻撃的な反応が寄せられたしかしながら人はこの物語によって心動かされその後奴隷制廃止運動へと駆り立てられることになった
その後数年間でストウ自身も活動的な社会運動家として名声を博していくことになる政治的集会や演説活動など多岐にわたり自ら進んで関与するようになりそれによって新たな支持者層とも繋がり始めた歴史家たちはこう語っている彼女こそ近代文学と社会改革運動との架け橋だった
年代には南北戦争が勃発し人の意識改革への期待感は高まっていたしかしそれにもかかわらず戦争という混乱状態から生まれる悲劇について多くの記事を書き続けアンクル・トムというキャラクター以上に深遠なるメッセージ性について伝え続けているこの時期おそらくストウ自身も国家分断という苦悩から完全には逃れ切れていないようだ
晩年には自身の日常生活にも変化が訪れた一人息子ヘンリーを亡くすという悲劇的出来事にも直面しその心痛はいかばかりであったろうしかしこの経験こそ彼女にさらなる創造力と言葉による癒しへの力強い欲望を与えたとも言えるそして年生涯年目の日まで多様な著作活動を続けながら世俗との別れの日へ向かってゆっくり進んで行った
私たち全員人類なのだ
この言葉は生涯通じてストウ自身が訴えていた価値観でもあり一つ一つ丁寧につむぎ出された物語でもあるこの精神こそ現代社会にも通じ我を意識することで真実へ近づいて行こうとの呼びかけなのであろうそれゆえ今日でもその影響力はいまだ色褪せず新しい世代によって再評価され続けている
死後約年経過した今なお響き渡るメッセージ
皮肉だろうそれほど時間が経過しているとは思えないほどアンクル・トムの小屋から受け取る感情波紋やメッセージ性はいまだ色褪せない
ブラックライフズマター のスローガンさえ耳目につき新しい世代によって再びスポットライトに照射され続けている現状を見る時おそらくビーチャー・ストウ自身も驚嘆することであろう人間として何より大切なのは互いへの理解と思いやりなのだその証明として歴史上最初となる小説アンクル・トムこそ奇跡的存在と言えるだろうそしてそれだけではなく彼女自身そのものこそ一度体験した悲劇と思慮深さという賜物すべて大切な財産だったのである