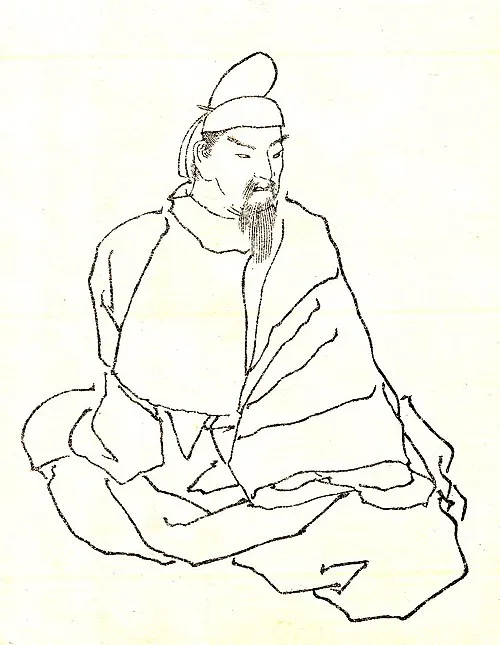生年月日: 1138年
没年月日: 1192年7月19日
出身時代: 平安時代
職業: 公卿
名前: 藤原師長
年建久年月日 藤原師長平安時代の公卿 年
年の夏建久年の月日平安時代の公卿・藤原師長は運命の波に翻弄されることとなるこの日は彼が歴史の舞台に立つ契機となったしかしその背景には多くの陰謀と苦悩が渦巻いていた生まれた時から彼は貴族として育ち多くの特権を享受していたがそれにもかかわらず心には常に重圧があった
年に生まれた藤原師長はその家系が持つ名声を背負いながら成長した幼少期からその知性と才覚を周囲に示しておりおそらく父親や祖父から受け継いだ政治的な感覚が養われていたのであろうしかしそれにも関わらず彼は常に他者との競争を意識し自身の立場を脅かす者たちへの警戒心を抱いていた
師長は若き日に公卿として任命されその地位によって彼自身もまた権力闘争という厳しい世界へ足を踏み入れることになった教科書では単なる役職として語られることも多いが実際には数え切れないほどの策略や裏切りが渦巻く場所であったそれにもかかわらず藤原家という名門で育った彼には一種特権的な安心感も存在した
皮肉なことに時代背景として武士階級の台頭があり公家社会は次第にその地位を脅かされていく運命にあった武士たちによる抗争や派閥争いの日 そして源平合戦この激動する時代で藤原師長はどんな選択肢を持っていただろうか議論の余地はあるもののおそらくその選択肢は極めて限られていたと言える
年源氏との戦闘によって平家政権は崩壊しこの動乱期において藤原師長もまた重要な役割を果たす必要性が出てきたしかしこの新しい秩序それこそ鎌倉幕府成立へと続く道筋への適応には大きな試練と痛み伴う選択肢しか残されていなかったある歴史学者によれば平安時代末期公卿と武士との間で新しい政治的関係性が構築されたと語るようだ
年日本史上初めて鎌倉幕府という新しい体制が確立されこの変革こそ藤原師長自身にも影響する出来事だったただこの変化には多大なる対立や不満も存在したそれでもなお当時として最良とも言える判断つまり新勢力との協調こそ彼が直面する試練だったその後間もなくして高位高官という称号から降格させられる羽目になり自身と一族への信頼性までも問われる事態となった
今振り返れば本来ならば自分自身と一族その名声さえ守るため全力で抵抗した方がよかったとも思えるしかし皮肉なことに何もしないままでいることで状況悪化のみならず多大なる恥辱まで被ってしまう結果となってしまったおそらくこの頃になると宮廷内で圧倒的少数派となりつつあった藤原氏への冷たい視線や批判から逃れる術など考え得ぬことであろう
死去する年まで放置されたようにも見えるこの遺産後世では失脚という単語ばかり目につくだろうしかしながら歴史上重要なのはその短い栄華だったと言える当時流行した言葉無常観無情さゆえ流転し続け変わりゆく様子これこそ現実そのものだったその証拠とも言えるエピソードも伝わっているある日突然大臣職から引き離された挙句そんな声すら聞こえてきそうだ
しかしながらそれだけではない未曾有とも言える権力基盤崩壊等新興勢力武士との連携強化など様な策謀について熟考していただろうまた不遇・不当と思われたり等悲劇的展開とは裏腹反対面でも色あったのでしょうむしろ諸事情複雑化して困惑された結果見えてこない何かについて論じてもよかったと言われていますでも結局結びつかなかったため無駄になる部分多発
最終的には歳即位元号改正歳当初より始まり年間在任中・御所詰め状態など制度改革進行こうしたエピソード含む故人周囲情報収集行為などどんな意味合いや価値付与可能だったのでしょう記録残すこと意義あるもの捉えて再考察促進必要同じ状況下だからこその思慮深さ求めたいですねこの流れ断絶防ぐ知恵とか気概求めたいところです