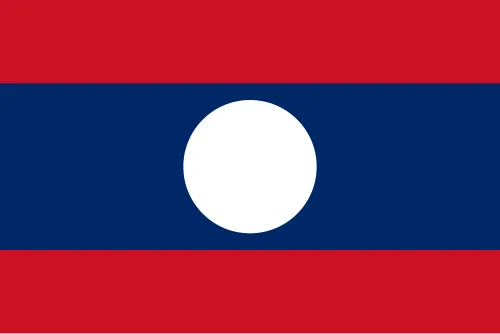日本人宇宙飛行記念日宇宙の彼方に見た夢と誇り
日本人宇宙飛行記念日は年に秋山豊寛氏がソビエト連邦のミール宇宙ステーションで約一週間を過ごしたことを記念して制定されていますこの出来事は日本における宇宙開発の歴史において画期的な瞬間でした秋山氏は初めて日本人として地球の大気圏を超え無重力状態を体験したことで多くの国民に夢と希望を与えました
この記念日は科学技術や教育の重要性を再認識させるだけでなく日本が国際社会においてどれほど成長してきたかその証でもあります以前は月への挑戦など遠い夢だと思われていた宇宙探査が現実となった瞬間でした
星への旅路未知なる世界への挑戦
年月日秋山氏が打ち上げられたその瞬間多くの視線が空へと向けられました青い空から放たれるロケットが大地の音を振動させながら高く舞い上がっていく様子は多くの人にとって忘れられない光景ですああ本当に行ったんだその瞬間誰もが息を飲み込みました
彼はミールに到達するとその無重力環境で浮遊しながら研究や実験を行いましたその様子はテレビ越しにも多く伝わり多くの子供たちや大人たちにも影響を与えましたその後星への旅路はさらなる探査へと繋がり日本も国際的な宇宙開発へ貢献するようになりました
夜明け前新しい時代の幕開け
この日から日本国内でも科学教育や宇宙関連産業への関心が高まり始めました学校では何故空に行かなきゃならないんだろうという疑問からどうすれば私も宇宙飛行士になれるかという夢を見る子供たちまで現れるようになりましたそして数年後には日本初となる本格的な有人宇宙船こうのとりが誕生しました
秋山氏以降も多くの日系 が活躍し続けていますその中には若田光一さんや野口聡一さんなどがおりそれぞれ独自なミッションで国際的な舞台で活躍しています彼らによって新しい世代へ受け継がれていく夢がありますそれは自分自身だけでなく日本全体として成し遂げたい目標です
子供の思い出帳未来への希望
私もいつかコスモスを感じてみたい
それぞれのお母さんお父さんもまた自分自身をご両親から受け継ぎ昔話として伝えていることでしょうあなたのおじいちゃんも言っていたわ空には星だけじゃなくて人類全体につながる可能性があるそう語る姿勢こそこの日付によって生まれる伝統なのですそしてこの思い出帳には一つ一つ未来への希望として綴られているのでしょう
未来はここにある
(中国古典『道徳経』)より道無為而治之 何もしないことこそ真実だとも言えるでしょうしかしそれとは逆説的ですが人類は常に動き続けている存在なのですここ日本でも新しい技術や知識によって進化し続けていますこの記念日はただ過去を見るものではなくそれこそ未来につながる一本目立つ線引きとなっています