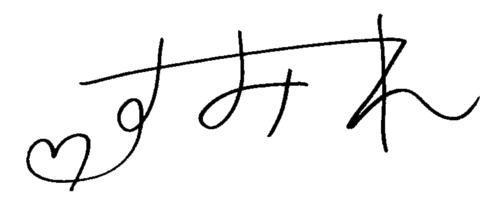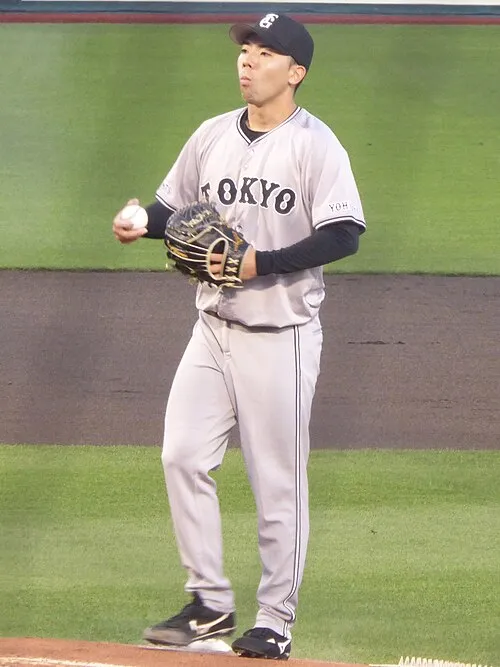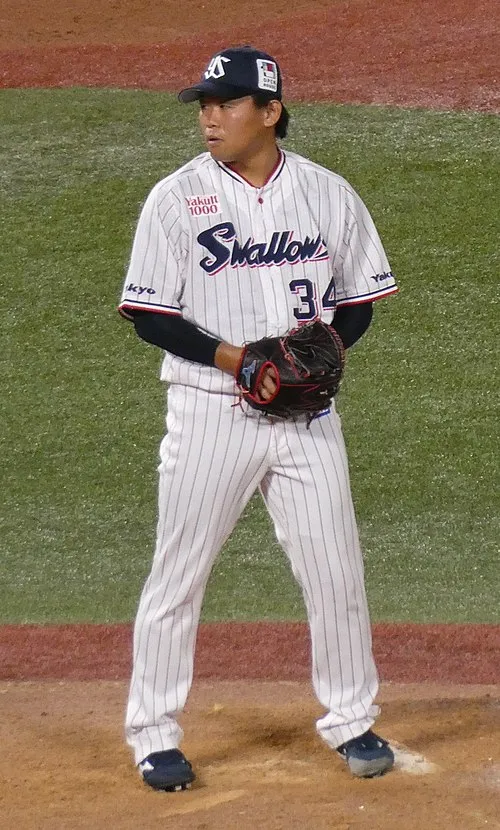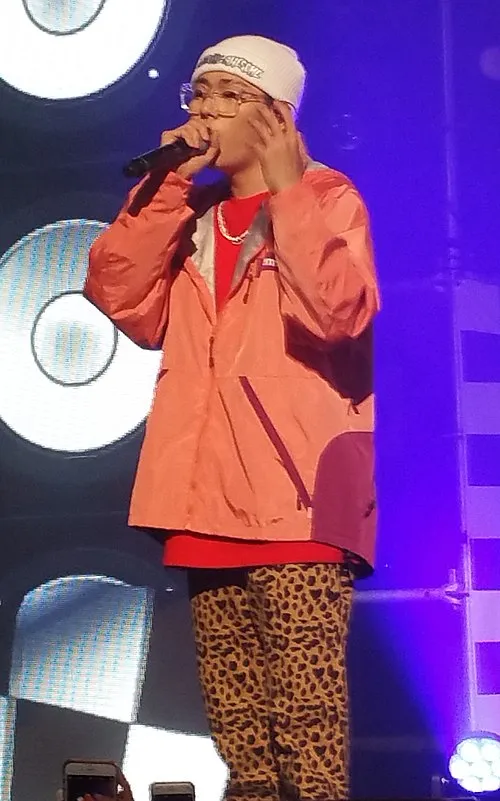2023年 - 阪神タイガースが18年ぶりにリーグ優勝。
‹
14
9月
9月14

十字架称賛の日(カトリック教会)の意義と祝い方
十字架称賛の日、または「十字架の高き礼拝の日」として知られるこの特別な日は、カトリック教会において非常に重要な意味を持っています。毎年9月14日に祝われるこの日には、キリストの十字架を通じて表現される救いのメッセージが再確認され、人々はその神聖な象徴に感謝し、崇敬の念を捧げます。この日は、キリスト教信仰における贖罪や希望の象徴としても広く認識されています。歴史的には、この日の起源は4世紀まで遡ります。エルサレムで見つかったとされる聖十字架が崇められ、その記念として設定されたことから始まります。特に、聖ヘレナ女帝がこの十字架を発見したことで知られており、その出来事は多くの信者によって「神秘的な導き」として語り継がれています。それ以来、この日には特別なミサや儀式が行われ、人々は心から信仰を新たにする機会となっています。愛しき者への贈り物:命あるものへの感謝この日、多くの人々は自分たちの家族や友人と共に集まり、共通の信仰を祝います。その場には赤いキャンドルや白い花が飾られ、穏やかな香りとともに祈りが捧げられます。「主よ、この地上で私たちにも愛する力を与えてください」という言葉が空気中に漂う中、多くの人々が静かに耳を傾けます。そこでは過去への感謝だけでなく、新しい希望へ向けた決意も交わされています。夜明け前…光輝く道筋夜明け前、人々は曙光とともに目覚め、新たな一日への期待感で胸が高鳴ります。この朝、多くの場合教会へ足を運ぶ準備をし、それぞれ心温まる服装で装います。街角では地元住民同士がお互いに挨拶し、「今日こそ十字架称賛の日だね!」という声が響き渡ります。それぞれ胸いっぱいになった思い出とともに教会へ向かう姿には、一種独特な緊張感さえ漂っています。そこでは、一年で最も美しい花々や装飾品で飾られる祭壇があります。そしてその祭壇上には、美しいキャンドルライトが灯され、それぞれひっそりと思い出や願望について思い巡らせています。その瞬間、自分自身もまたその一部なのだという実感。そして「すべては天から授かっている」という深遠なる思想につながってゆきます。子供の思い出帳:無邪気さとの交わり子供たちは大人たちよりも直観的です。この日、小さな手でもてあそぶ祭壇のお花やロウソク。「これって何?」との問いかけには、大人たちは何度でも答えることでしょう。「これは神様へのプレゼントなんだよ」と。その瞬間、大切なのは知識以上です。無邪気さ、それ自体こそ信仰です。The sounds of laughter blend with the solemnity of prayer, a beautiful contradiction that defines this sacred day. The aroma of fresh bread and baked goods wafts through the air, as families gather to share meals in celebration. This moment is not just about ritual; it’s about community, love, and shared beliefs.全てここから始まった:復活への旅路This day also marks the beginning of a reflective journey towards Easter...

日本のセプテンバーバレンタイン:愛と友情を祝う独自のイベント
セプテンバーバレンタイン、これは日本における独特な愛と友情を祝う日として知られています。この日、特に女性が男性にチョコレートを贈るという風習は、日本の文化に深く根ざしており、1970年代から広まりました。最初は企業のマーケティング戦略から生まれたものですが、今では恋人同士や友人との絆を深める重要な日となっています。この日が持つ意味は、ただ単に甘い贈り物をすることだけではなく、人々の心を結ぶ温かさや思いやりを表現する機会でもあるのです。日本各地で行われる様々なイベントやプロモーションも、この祭典への期待感を高めています。また、世代によって異なる解釈もあり、それぞれがこの日の過ごし方や意味合いを楽しんでいます。愛のメロディー:心と心が交わる瞬間想像してみてください。街中がピンクと白で彩られた2月、その空気には甘いチョコレートの香りが漂い、人々は笑顔であふれています。そんな中、一歩踏み出した瞬間、誰か特別な人への思いを込めたチョコレートを手渡す。それはまるで、自分自身の一部をその人に捧げるような、不思議で美しい瞬間です。夜明け前… 新しい愛への扉セプテンバーバレンタインの日が近づくにつれて、多くのカップルや友人たちは緊張と期待感で胸が高鳴ります。「今年こそ告白するぞ!」と決意した若者たち。その背後には、不安と希望が入り混じった複雑な思いがあります。しかし、そのドキドキ感こそ、この日ならではの魅力なのです。夜明け前、小さなカフェではまだ薄暗い中、一杯の温かいコーヒーと共に小さなチョコレートボックスが並べられている光景。ここでも新しい物語が始まります。「これ、お前への気持ちだよ」と言う言葉は、おそらく何よりも強力な魔法なのです。子供のお菓子帳:無邪気な友情また、この日は子供たちにも特別です。学校では友達同士で交換し合う手作りのお菓子、大切なのは値段よりもその心です。「君には特別なお菓子だよ!」そんな言葉には大きなお金なんて必要ありません。ただただ純粋な友情と思いやりだけで十分なのです。この無邪気さこそ、大人になっても忘れない大切な要素なのだと思います。そして、この日は毎年繰り返されます。それぞれの家庭や地域によって異なる伝統や慣習があります。それでも、日本全国どこへ行っても感じられる「愛」のメッセージ。それは時代を越え、多世代へ受け継ぐ宝物となっています。風景画:それぞれ描く“愛” の色合い季節ごとのイベントとは違った独自性として、このセプテンバーバレンタインの日。その様相は多様性豊かな日本社会そのものと言えるでしょう。一見シンプルながらも、それぞれ違った色合いやニュアンスがあります。そして、それらすべてが「愛」というテーマによって一つにつながっています。道端に咲く桜並木、その下通るカップルたち。そして彼らがお互いに贈り合うチョコレート。その姿を見ること自体、また他者との絆について考えさせてくれる瞬間でもあります。"君との距離" が生む優しい時間"君との距離" という言葉。一見抽象的ですが、その実体験から感じ取れるもの、それこそこの日に求められている感情ですね。この日は親しい仲間同士だけじゃなくて、「あまり話したことないあいつ」に向けても小さなお菓子一つ用意したりすることで、新たなる関係性につながったこともあるかもしれません。それ故、「知らないあなたへ贈ります」というその勇気、とても素晴らしくないでしょうか?"時空" を超えたメッセージ昔から続いてきたいろんな儀式・祭典とは少し違っている面白さ。この日の普遍的テーマ、「贈与」の中にも古来より受け継ぐ祈念・願望的側面がありますね。"伝えるため" "結びつきを確立するため" それだけじゃなく、自分自身・相手へのメッセージとして響いています。「未来永劫まで続きますよう」にという願望、その背景には懐かしき先祖伝来から何千年もの知恵があります。そして今、それぞれ新しい形態へ進化している最中ですね。...

コスモスの日:日本の美しい秋を祝う日
コスモスの日は、日本において毎年10月1日に祝われる特別な日で、主に秋の訪れを感じさせる美しい花であるコスモスを讃える日です。この日は、自然とのふれあいや環境保護の重要性を再認識する機会でもあり、日本各地で色とりどりのコスモスが咲き誇ります。コスモスはその花言葉として「調和」や「愛情」を持っており、人々に平和と安らぎをもたらす存在として親しまれています。歴史的には、1979年に始まったこの日には、国民が花々と向き合い、その美しさや大切さについて考えることが求められてきました。日本では秋になると、田んぼの周囲や公園などで鮮やかなピンクや白、赤色のコスモスを見ることができ、多くの人々がその景観を楽しみます。つまり、この日はただ単なる一日のイベントではなく、日本人に根付いた文化的な側面とも深く結びついていると言えます。風に揺れる思い:秋空の下で青空が広がる中、風に揺れる淡いピンク色のコスモス。まるで小さな妖精たちが舞っているかのようです。その香りは清々しく、一歩近づくとふんわりとした甘さに包まれます。この日、多くの家族連れや友人同士が集まり、その美しい光景をカメラに収めたり、お互い笑顔を交わしながら散策する姿は実に微笑ましいものです。子供たちは足元のお花畑へ駆け寄り、小さな手でそっと触れてみたり、その可憐な姿勢から様々な感情を見出していることでしょう。夕暮れ時…心温まるひと時夕暮れ時になると、西日の柔らかな光によって、一層神秘的な雰囲気となります。その瞬間、大地には金色の輝きが広がり、それこそ絵画そのものです。立ち止まり、目を閉じて耳を澄ませば、小鳥たちが歌う音や風による葉音、それから遠くから聞こえてくる子供たちの笑声など、この瞬間だけでも心温まります。「こんな景色を見るために生きている」と思わず口から漏れる言葉。そしてまた、「私たちも自然との調和」をテーマとして見つめ直す機会なのかもしれません。古より伝わる約束:生命への感謝昔から日本では四季折々のお花にはそれぞれ意味があります。また、「草木」に感謝し、生かされていることへの意識も深いものがあります。それは先人たちによって培われてきた文化でもあり、「与えられている生命」を大切する気持ちは今なお息づいています。この日に行う「植樹祭」なども、その一環として位置づけられており、新しい命への誓いや過去への敬意、とても重要です。「私たちは何もないところから生まれてはいない」という教訓もここには込められており、大切なのはそれを忘れることなく次世代へ受け継ぐということでしょう。伝説となった日:国民運動へ1980年代以降、この日はただのお祝いの日ではなく、環境保護活動として全国的にも注目され始めました。A地域では、自分達だけでなく全てのお花にも感謝しようという発想から、「世界中すべてのお花とも共存したい」という気持ちになりました。それまであまり関心が薄かった地域住民達も自分達のできる範囲内で支援活動等行うようになりました。そして、その流れは全国各地へ広まり続けています。それゆえ、日本全土で盛大なお祭りとして定着しました。 "光輝く未来への道筋" "その先鞭となった町"とは具体的にはA市ですが、この町では例年10月1日に盛大なお祭り騒ぎとなります。「未来につながった希望」=「自己表現力」の体現化だったようにも思います。そしてここでもまた、自分達だけではないという発想があります。それこそ世界中のお祭りごとの部分とも結びついた形と言えるでしょう。「私達だって生かされたい」と語っていた村人たち。しかし彼等自身だけでは成し得ない課題だったと言えるかもしれませんね。その繋ぐ相手探しこそ真実性(本物)なのだろうと思います。 "真実を見る目…" "本当なら何処まで進むべきなのだろう?"そんな疑問抱えつつ、人知れず変わろうとしていたその流星群…。私自身今この頃、多様性とは何か再考しています。"社会構造上バランサー(均衡者)” ある意味不確定要素役割担っちゃった部分です。"両親世代すればあそこまで辿れる筈だ…" それ故より深刻問題化してしまいました。”本当に平等?”果してそう言えるのでしょうか?無論難易度高かった所為?…いや実際進んできましたよね!それでも尚まだ完全解決出来ぬ問題抱えてしまった事実。」 "そしてこの歴史ある日だからこそ問いたい..." "勝利とは何処へ向かえば良かったのでしょう?""不完全ながら頑張っちゃいましたね"...
出来事
2020年 - アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計とジェームズ・クラーク・マクスウェル望遠鏡により金星の大気内におけるホスフィンの存在が確認される。本来金星はホスフィン生成に足る温度・圧力環境にないため地球外生命体の存在が示唆されている。
2020年 - 自民党総裁選挙で第26代自由民主党総裁に内閣官房長官の菅義偉が選出される。
2019年 - サウジアラビア、アブカイクに位置する同国最大の石油精製施設が空襲を受ける(サウジ石油施設攻撃)。報道を受けて各国の原油市場で原油価格が一時的に高騰。
2018年 - アメリカ合衆国ノースカロライナ州にハリケーン・フローレンスが上陸。16人以上が死亡し、数万戸の住宅に被害が出た。
2015年 - 重力波の初検出。
2015年 - 熊谷連続殺人事件。
2013年 - 内之浦宇宙空間観測所からイプシロンロケットの初号機が打ち上げられる。
2008年 - 2008年コンゴ民主共和国サッカー暴動が発生。
2007年 - 月周回衛星かぐやの打ち上げ成功。
2007年 - イギリスの銀行ノーザン・ロックで取り付け騒ぎ。
2001年 - 任天堂がニンテンドーゲームキューブを日本で発売。
2000年 - Microsoft Windows Millennium Editionがアメリカで発売、日本は9月23日。
1999年 - キリバス・ナウル・トンガが国連に加盟。
1994年 - メジャーリーグでのストライキを受けてワールドシリーズ中止が決定。
1994年 - 住友銀行名古屋支店長射殺事件。
1994年 - プロ野球のオリックス・ブルーウェーブのイチローが192本目の安打を放ち、年間安打数の日本新記録を樹立。同シーズンでは最終的に210安打を記録。
1993年 - ルフトハンザドイツ航空2904便事故。
1991年 - 台風17号が長崎市付近に上陸。日本海沿岸部を縦断し、全国で11人が死亡。
1990年 - 本田技研工業がNSXの国内販売を開始。
誕生日
死亡
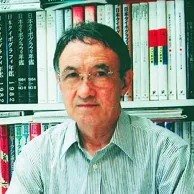
2023年 - 篠原榮太、グラフィックデザイナー(* 1927年)

2022年 - ヘンリー・シルヴァ、俳優(* 1926年)

2022年 - イレーネ・パパス、女優(* 1926年)

2021年 - ユーリ・セディフ、ハンマー投げ選手、1976年モントリオール・1980年モスクワ五輪金メダリスト(* 1955年)

2021年 - ヴィクトル・カザンツェフ、軍人、政治家、元南部連邦管区大統領全権代表(* 1946年)
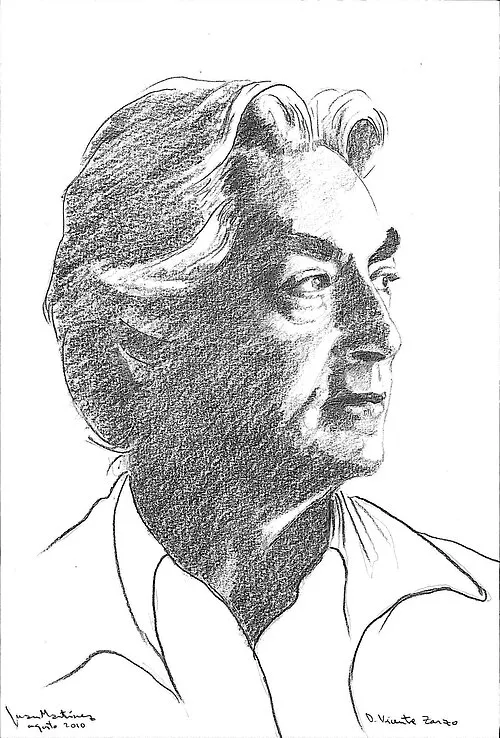
2021年 - ビセンテ・サルソ、ホルン奏者(* 1938年)

2021年 - 趙鏞基、牧師、汝矣島純福音教会創立者(* 1936年)

2020年 - ビル・ゲイツ・シニア、元弁護士、慈善家、ビル・ゲイツ実父(* 1925年)

2019年 - ジーン・バッキー、元プロ野球選手(* 1937年)
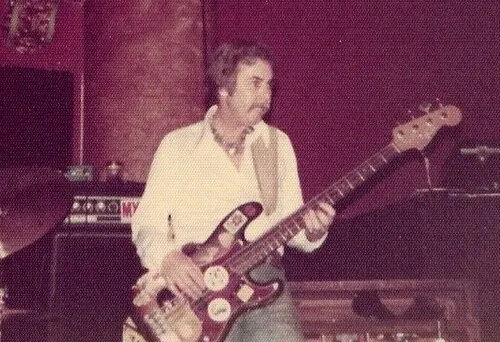
2018年 - マックス・ベネット、ジャズベーシスト(* 1928年)