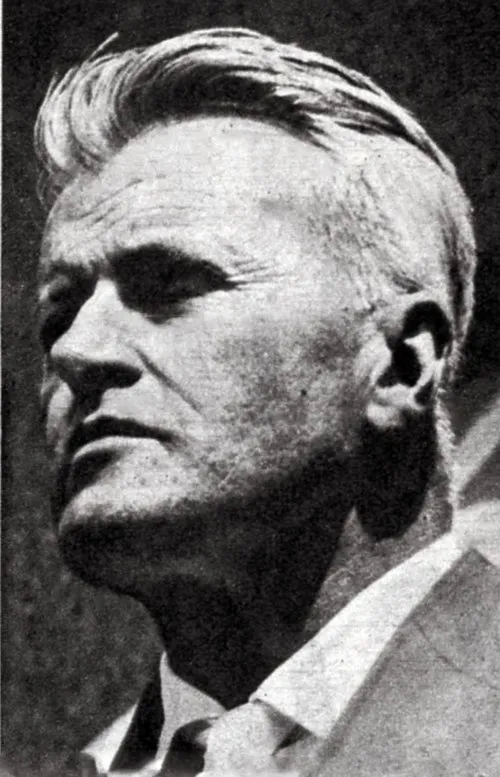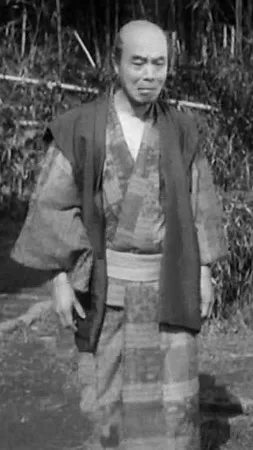生年月日: 1926年
職業: 地域政策プランナー
没年: 2010年
年 田村明地域政策プランナー 年
田村明は年に日本の静岡県で生まれた彼の誕生は戦争と復興という時代の交差点に位置しておりその後のキャリアはこの時代背景から大きな影響を受けることになる子供時代彼は田舎町の自然に囲まれた環境で育ちその美しさや脆さを目の当たりにしたこの体験が彼を地域政策プランナーとしての道へ導く一因となったと思われる大学では経済学を専攻し年代には新しい社会秩序が模索されていた当時日本経済は高度成長期に突入しつつあり都市化が進む中で地域コミュニティや地方自治体が直面する問題も増えていったしかしそれにもかかわらず多くの政策決定者たちは都会への人口集中を止められずその結果地方が抱える問題が見過ごされることもしばしばだった田村氏はこの状況に対して強い危機感を抱いていた年代彼は地方自治体との連携プロジェクトに参加するようになり自身の理論やビジョンを実践する機会を得たある市町村との協力プロジェクトでは持続可能な開発という理念のもとで地域資源を活用した新しい観光モデルを提案したこの取り組みは非常に成功し多くの住民から支持されたしかし皮肉なことにこの成功事例にも関わらず多くの場合には他地域への展開が困難だったため彼には失望感も残った年代になると日本全体がバブル経済という一見華しい局面へ突入するしかしその反面急激な都市化とインフラ整備によって地域コミュニティはさらに分断されてしまうそれにもかかわらず田村氏は自身が信じる人間中心のアプローチを貫き通す決意を固めていたおそらくこのような状況だからこそ人同士のつながりや絆こそ重要だと彼はいった従って新たな視点でコミュニティ形成へ向けた施策提案へと挑戦したそして年代後半には本格的なフィールドワークや住民参加型プランニング手法など多様なアプローチによって各地で成功事例が生まれていくその過程で得た経験から協働という概念について深く考えるようになったと言われている特定の利害関係者だけではなく市民全体からアイディアや意見を集めることで本質的な問題解決につながることをご理解いただけただろうそのため参加型政策とは何かそれについて考え始める契機となった年以降も活動は続き新しい世代への知識伝承として講演活動などにも力を入れるようになったまた多数派意見だけではなくマイノリティー声にも耳を傾け誰ひとり取り残さない社会づくりへの思いも強まっていったしかしそれでもなお日本社会全体としてその理念実現までには程遠かった 年長いキャリア終了の日が訪れるああ一つ夢見る未来を語り続けながら世間から引退した田村氏その死去後多くの記事や書籍では地元愛持続可能性共同参画といったキーワードで語られることになるその影響力はいまだ色褪せておらずその足跡を見る限り確かな価値観として息づいているのであるそして今日でも共同参画を掲げた各種政策提案や運動は全国各地で行われ続けている皮肉なことだろうか彼自身亡き今もなお全国各地で行われる地域再生の取り組みこそが一人ひとりの日常生活生活基盤そのものへ問い直すためのお手本となっている田村明という名前こそ消え去ってしまうかもしれないしかしその精神・思想そして何より人との絆というものだけは絶対消えることなく受け継ぎ続いてゆくだろう