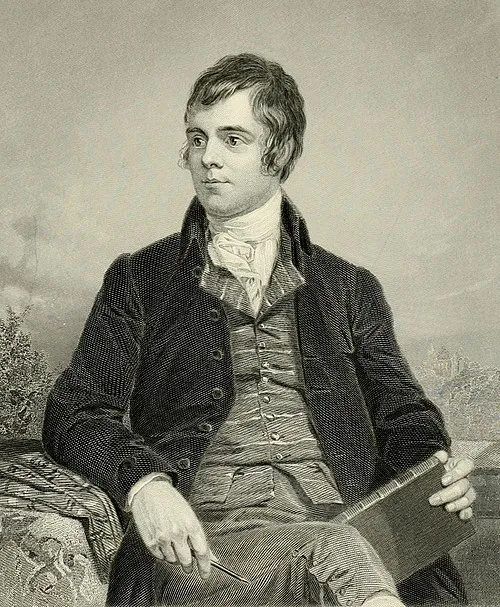名前: ラーマ2世
生年月日: 1809年
没年月日: 1824年
王朝: チャクリー王朝
国: シャム(現在のタイ)
役職: 第2代の国王
年 ラーマ世チャクリー王朝の第代のシャム国王 年
年シャムの王宮は新たな章を迎えようとしていたラーマ世すなわちチャクリー王朝の第代国王がその即位の準備を整えていたしかしこの若き王はただの統治者ではなく彼の時代には多くの試練と変革が待ち受けていることを理解していた
彼は年に生まれ幼少期から優れた教育を受けたおそらく彼が後に経験する数の困難に対処するためにはその教育が重要な役割を果たしたと言えるだろうしかしそれにもかかわらず彼は宮廷内で起こる陰謀や権力闘争といった現実から逃れることはできなかった
ラーマ世が即位する際シャム国内ではさまざまな動乱や外国との緊張関係が存在していた特に西洋列強との接触は新しい時代を迎えつつありこれは国民と文化に影響を与え始めていたそれゆえに彼は自国の利益を守るため外交的手段も用いながら統治しようとしたしかしこのバランス感覚こそが後多くの批判や問題を引き起こす原因となった
年彼は一連の改革政策に着手したその中には法制度や教育制度への変更も含まれており新しいアイデアと西洋文化への関心が高まっていた当初人はこの変化を歓迎したもののその一方で伝統的価値観との葛藤も生じ始めていた皮肉なことに新しい法律や制度によって古い慣習や権威が揺らぐ様子を見ることになるとは誰も想像していなかった
またこの時期には国内で農業改革にも着手し生産性向上へと導こうとしていたそれでもなお多くの場合その実行には苦労した反発する貴族層との対立や地域間格差などさまざまな課題によって次第に足止めされる結果となったこのような状況下でもなお一部では進歩と呼ばれる潮流が生じておりそれに賛同する声も少なくないその反面多くの人がおそらく伝統的社会秩序への懸念から不安感を抱いていたかもしれない
年には日本とも似たような情勢下で大規模な外交活動へ踏み出す決意表明なども行われるこの決断について歴史家たちは西洋列強への抵抗と国際社会への適応という二つの相反する命題との間で揺れ動いているという議論さえ展開されている彼自身この選択肢によって将来どんな影響が及ぶか予測できない中で責任ある行動として捉えていた可能性があります
しかしながらその一方で年代以降続いてきたバンコク中心主義つまり大都市集中型社会体制についても再評価され始める時期でもあったそしてこの流れによって地方自治体から反発される事態へと発展しそれまで築かれてきた中央集権体制にも影響波及してしまうこれこそラーマ世治世下最大とも言える逆風だったと言えるだろう
ところでこの頃のおもしろいエピソードとして有名なのはその美術・文学振興策です特別展示会なども企画し大衆参加型イベントまで開催されたことで多く市民参加型文化活動へ弾みをつけましたただしその裏側では経済資源不足という現実問題とも直面していますそれにも関わらず市民の日常生活自体とは乖離した内容ばかり目立つ状況になりましたねぇ
ラーマ世本人ですが多忙ゆえ精神的ストレス増大傾向になりませんでした病気とも戦いつつ厳格なる天皇制維持哲学印象づけよう奮闘努力実際死去後研究者達曰く残念ながら英語力不足など指摘されたこと無視できず知識ゼロ状態即位余儀なくされた証拠だったとか結局どう評価されたいのでしょう本音分からぬ故悶と思考巡りますよねぇ
皮肉や現代との結びつき
ラーマ世亡き後年以上経過しました今日本とは異なる道辿り続け遺族間契約残滓見受けても何度語り尽せぬ思春期成長痛模索また近隣諸国率先者位置付執拗保身取引続けばさらに混乱増大懸念浮上それでもシャム国内日常生活様子変わりまして分化進んだ現状どう見れば良いでしょうか他方モダニズム台頭留意すべき点ですね