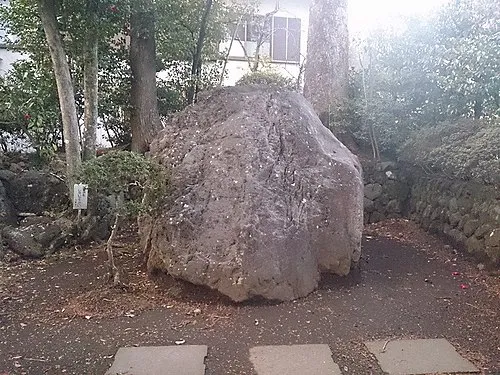生年: 1835年
没年: 1894年
職業: 根付師
活動時期: 19世紀
年 尾崎谷斎根付師 年
年江戸時代末期の日本で一人の男が生まれた尾崎谷斎彼は後に根付師として名を馳せることになるしかし彼の人生は単なる技術者としてではなく日本の伝統工芸において重要な役割を果たす運命にあった
若い頃から絵を描くことや彫刻に興味を持っていた尾崎はその才能を開花させるために学び続けた数多くの師匠から技術を学びながら自身のスタイルを確立していったしかしそれにもかかわらず職人として認められるまでには長い道のりが待っていた彼が本格的に根付け制作に取り組み始めた頃日本は明治維新という大きな変革期を迎えていた
年新政府が発足し西洋文化が流入する中で日本の伝統工芸もその影響を受けていた尾崎はこの新しい時代への適応力が求められる状況下で古き良き日本文化と西洋との融合について考え始めるそれでもなお彼は自身の根付け製作技術には揺るぎない自信を持っていた
ある日彼は特注品として依頼された一対の根付け制作に取り掛かるこの作品には特別な意味がありその背後には依頼主と尾崎との間で交わされた深い思い出があったその作品こそ今でも語り継がれる月夜兎の根付けだったこの兎は月明かりの下で跳ねる姿が美しく表現されており多くの人から愛されることになるしかしこの成功にも皮肉なことに多くの日努力した結果だった
年日本全国でその名声が高まっている中尾崎谷斎という名前も広まりつつあったその頃には多くの弟子たちも育て上げており自身だけではなく次世代への継承にも力を注ぐようになっていた弟子たちとの交流によって新しいアイデアや技法も次第に芽生え始めその影響力はますます増していったのである
そして年不幸な知らせが舞い込む尾崎谷斎この偉大なる職人と師匠はその生涯を閉じることとなった死去した日多くのお悔やみや追悼文が寄せられただろうしかしおそらくそれ以上に残された弟子たちや友人たちは深い悲しみに包まれただろう
今日でも彼によって創造された根付け作品はいまだ多く存在しそれぞれ異なる物語と情熱を秘めているそれにもかかわらず多くの場合これら作品を見る機会すら少ない現実この時代背景とも重ね合わせれば不思議ではない月夜兎は今でも観光地や博物館などで展示されているもののおそらく彼自身よりも有名になってしまったのである
歴史家たちはこう語っている尾崎谷斎こそ日本文化とその精神性への架け橋だとしかしながら非常に興味深い点として新しい世代には必ずしもその名前と意味合いまで浸透しているわけではないという事実だ職人や工芸という言葉自体について問われれば答える者はいようとも尾崎の名まで知悉している者となれば極限される
年現在日本国内外問わず多様性への理解・共感も広まる中この過去の日へ振り返りますその時代背景・人物像・そして遺産まさしくそれこそ歴史的文脈なのだろうおそらくこれから先進化する文化や価値観とはまた異なるものとなり得ようよっぽど好き勝手好きだと言える伝統を守ろうと思えば意義など更なる光景へ問い直さざる負えません