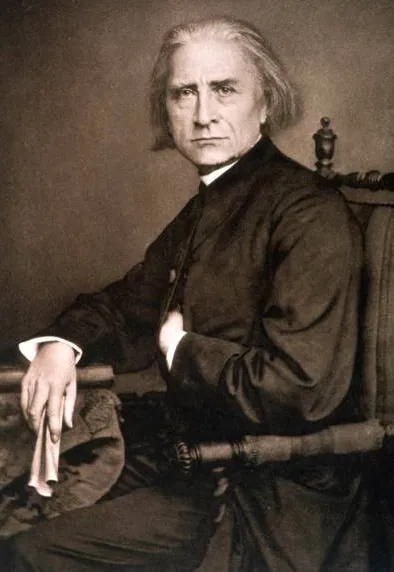生年月日: 1842年9月19日(天保13年)
職業: 外交官
身分: 華族
没年: 1906年
年天保年月日 長岡護美外交官華族 年
年の秋長岡護美は日本の北部越後の地に生を受けた彼が生まれたその瞬間誰もが彼の未来を予測することはできなかったしかしこの小さな命が日本の外交史に名を刻むことになるとは時代背景から考えると実に興味深い運命であった時代は江戸時代末期鎖国政策が続く中日本は外圧にさらされており明治維新へ向けて大きく動き始めようとしていた
幼少期から教養を重んじられた護美は西洋文化への興味を抱きながら成長したこれには皮肉な点もある当時の日本社会では西洋の影響が恐れられていたにもかかわらず彼自身はその魅力に惹かれていったのであるそして青年期には漢学とともに英語も学びその才能を見せつける機会が訪れるそれにもかかわらず日本国内では依然として武士階級による封建的な価値観が色濃く残っていたため彼には困難な道が待ち受けていた
年明治維新の勃発この出来事は護美にとって転機となった当時歳だった彼は新政府から外交官として任命されることになるしかしこの役職には多くの責任と期待が伴うものであったそのためおそらく彼は自身の日の選択や行動に対し大きなプレッシャーを感じていただろう国際社会との接触という新たな局面で日本という未成熟な国家を代表する立場になったことでその期待感や不安感はいっそう高まった
また他国との関係構築について論議される中護美自身もさまざまな交渉テーブルにつくこととなるしかし多くの場合それは容易ではなくさまざまな国際的トラブルや緊張状態が蔓延している中で行われたためだこのような状況下でも彼は冷静さを保ち自身だけではなく国家全体にも利益をもたらすべく努力したその姿勢こそが多大なる信頼を集める結果となりそれまで以上に注目される存在となっていった
年代初頭護美の外交キャリアはいよいよ成熟していくそして不平等条約と呼ばれる問題へ取り組む必要性が浮上したこの条約群によって日本人には外国人より低い法的地位しか与えられずその不満や反発心はいっそう強まりつつあったそれにもかかわらず長岡護美自身としてみれば大変デリケートで複雑な問題だった可能性があります他国との関係悪化だけでも非常事態なのだからそれでもこの課題への挑戦こそ自身のみならず次世代への架け橋ともなるべき使命だと感じていたかもしれない
年月日長岡護美この世から去るしかしその死後も彼の遺産と言える外交方針やアプローチについて議論され続けているそして驚くべきことにそれから年後日本国内外で未だ様な評価や意見交わす場面を見ることになるそれほどまでに影響力ある人物だったということだろうまた現代社会でも不平等条約解除運動など歴史的背景への理解なしには成し得ない状況でありその影響力はいまだ健在だと言えるだろう
現在では歴史家たちによって語り継がれる外交官・長岡護美皮肉にも日報道され続ける現代社会こそ多様性や複雑性人間同士の日常的なお付き合いについて考え直す契機ともなる政治とは何かこの問いかけ自体がおそらく過去から今まで一貫して重要視され続けているテーマなのだそしてそれゆえこそ人の日常生活へ密接につながり生き続ける存在なのである