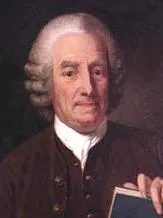名前: 稲妻雷五郎
生年: 1802年
死年: 1877年
地位: 大相撲第7代横綱
年 稲妻雷五郎大相撲第代横綱 年
稲妻雷五郎その名は日本の大相撲界において不滅の輝きを放つ存在であった年彼はまさに嵐のような運命を背負って誕生したしかしこの歴史的人物がその後どのようにして横綱となりそしてどんなドラマが繰り広げられたのか少し掘り下げてみよう
彼の少年時代は決して平坦ではなかった若き日の雷五郎は地方出身でありながらもその驚異的な体格と運動神経を持っていたしかしそれにもかかわらず周囲から期待されるほどには恵まれた環境ではなく自身を鍛え上げるためには厳しい努力が必要だったそれでもなお彼は相撲への情熱を失うことなく自らの道を切り開くこととなった
年代に入ると稲妻雷五郎は名門・山梨部屋に入門することになる最初は多くの仲間たちと同じように無名であったがその力強い取り組みや独特な技術によって瞬く間に注目を浴び始めたそして皮肉なことにこの時期には既存の横綱たちとの厳しい競争も待ち受けていたしかし彼はその試練すら楽しむかのように乗り越えていった
年代中頃になると彼は徐にその実力を証明し多くの勝利を収めていく特筆すべきは年その年大関として初めて臨んだ番付戦で見せた圧倒的な強さだ一度負ければ二度と這い上がれないと言われる相撲界で一度も敗北することなく全勝したという伝説的な事績は今なお語り草となっているこの偉業によってついには年大相撲第代横綱へと昇進する
しかしその栄光の日も長続きしなかったそれにもかかわらず多くのファンや仲間から支持され続けた理由としておそらく彼自身が持つ人間的魅力が挙げられるだろう稲妻雷五郎が土俵外でも多様な社会活動や文化振興にも積極的であったため人から愛されたのであるそしてそれゆえなのかあるファン曰くまるで日本人全員から愛される存在だったという声もあったほどだ
年日本では新しい時代へ向けて動き出していたその中でも稲妻雷五郎自身も様な変革を迎え入れる準備をしていたと思われたしかし皮肉にもこの年こそ彼の日常生活には波乱が待ち受けていた病気や怪我など次と訪れる困難それでも逆境こそ成長につながるという信念だけは失わずとても前向きだったと言われている
ところが年代初頭になんとか復帰したものの一時的とは言えそれまで培ってきた影響力やカリスマ性とは裏腹に周囲との摩擦や問題点も増えていった老化現象とも戦いつつ自分自身だけではなく新世代への教え込みにも時間とエネルギーを費やしたこの挑戦こそ本当ならば安穏として過ごせても良かった日常生活への反発だったとも考えざる得ないその背景には自分だけではない新世代にも道筋を示すという意識が強かったのであろう
残念ながら年代になってしまうと体調面から来る悩みなども顕著になり年月日ついには享年歳という驚異的長寿ながら静かなる人生幕引きを迎える一説によれば最後まで毅然として舞台立つ姿勢はいまだ記憶され続け土俵上手足自由などと語られているただし不運とも言える形態のお別れ方ゆえ今この瞬間生き抜いてほしかったと望む者も少なくないことでしょう
今日でも稲妻雷五郎という名前について多方面から評価され続けています真剣勝負の精神観など根底部分こそ大切ですが同時に人付き合いや思いやり等普遍性ある資質さえ引き継ぐべきなのですという意見も数多く聞かれますまた日本相撲協会で使われる用語集等では神格化された姿勢以上とも捉える場合がありますつまり現代社会へ移行してなお良好なるイメージ創出せんと言わんばかりでしょう