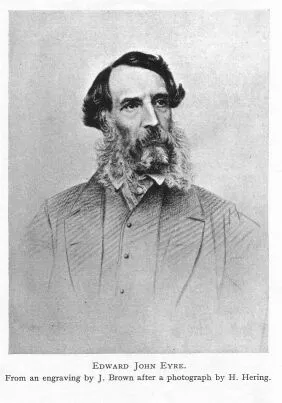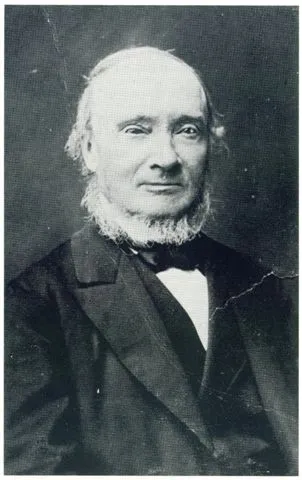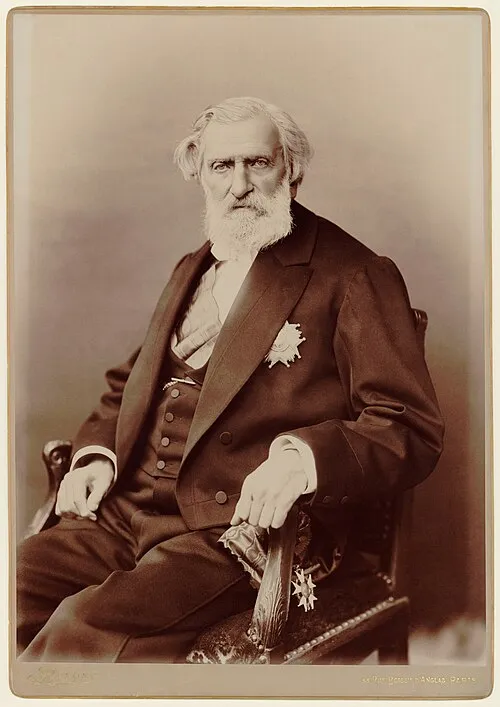生年: 1844年
死年: 1930年
職業: 画家、彫刻家
国籍: ロシア
代表作: 「ボルガの舟引き」「イワン・グローロフの肖像」
年 イリヤ・レーピン画家彫刻家 年
年ロシアの貴族の家に生まれたイリヤ・レーピンはその画材を握る手にすでに運命的な使命が宿っていた彼の名は後に芸術界で響き渡ることとなるがその道のりは決して平坦ではなかった
幼少期レーピンは周囲の自然や人からインスピレーションを受け取ったそれにもかかわらず彼の家族には厳格な教育方針があったため自由な発想を持つことは容易ではなかったおそらくこの経験が彼を後の作品で人間存在の深い感情と苦悩を描写するアーティストへと育て上げたのである
年まだ若干歳だったレーピンはサンクトペテルブルク美術学校に入学し本格的な芸術教育が始まったしかしこの決断は彼自身と家族との間に緊張をもたらした伝統的な価値観に従う父親との対立それでも彼は画家としての道を進むことを選んだ
年代にはパリへ渡り西洋絵画や印象派から影響を受けながら自身独自のスタイルを模索するしかしこの時期にはロシアというテーマへの強い愛着も芽生え始めていたそのため多くの作品では民衆や労働者の日常生活が描かれるようになるそして年にはボルガ河岸で歌う労働者を発表しその社会的リアリズムが高く評価されるようになった
年代になるとイワン雷帝とその息子といった作品によってその名声は頂点へと達するしかしそれにもかかわらずレーピンは満足しない性格だったそれどころか自身のアイデンティティーや創作への飽くなき探求心から新たな表現手法へ挑戦する姿勢を崩さない皮肉にもその探求心こそが彼自身を苦しめ続ける要因とも言えるだろう
またレーピンには独特な視点で人物像だけでなく風景画も描写した才能もあった北方の日没など美しい自然風景に触れ合うことで彼自身も癒されているようだこの時代多くの場合芸術家たちは個人主義から解放されて社会全体へのメッセージ性すべて他者との関わりから生まれるものとして捉えていたしかしそれでもおそらくその中でも最も真実である自己表現という課題への渇望こそ本質的だったのである
年代初頭にはフランスへ戻り新しい技法やスタイルとの接触によってさらなる革新が図られたその一方で母国ロシアでは急速に政治状況が変わりつつありそれによってレーピン自身も大きな影響力を持ち続けることとなる年月革命後多くの芸術家同様に再び社会的責任について考えさせられながら活動していったつまり今何を書くべきなのかという問いだまたこの時期多くのでこぼこの運命というものを見ることになる悲劇的とも言える移行期だと言える
年まで生涯作品制作や教育活動にも積極的だった氏その間中立地帯として機能する場所例えばフィンランドなど外部環境とのバランスもうまく保ちながら過ごしたとも言われているまた私生活では幾度もの挫折や愛情関係など人間味溢れる人生模様を見ることになる
年月日生涯歳で亡くなるまで多彩なる色彩と思索によって形成された数多のお宝絵画不幸にもその生命線とは反対方向へ向かった多面的存在感ゆえ遺産として残された歴史評価そのものという価値創造ただ一つ確かなことそれはいまだ人の日常生活や思考過程等今日でも無限なるインスピレーション源になり続けていると言えるそしてこうした背景故この記憶となればますます代替不可能になる流動性故忘却されぬ存在感抜群すぎた現代陶酔とも言える仕掛けなのであろう