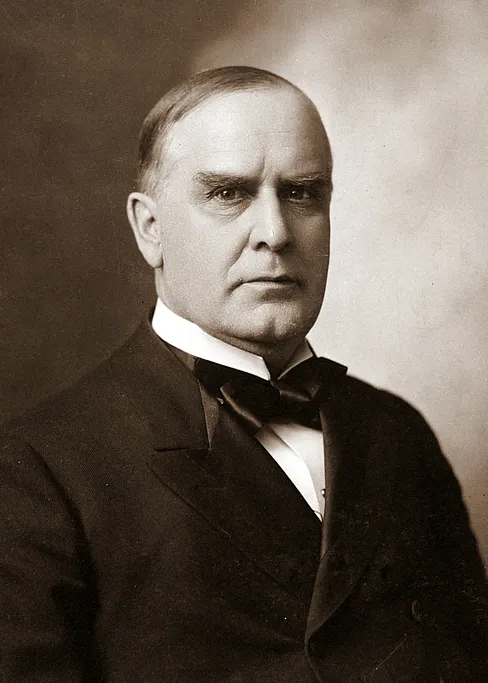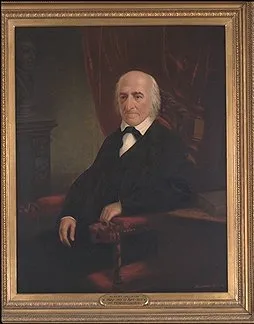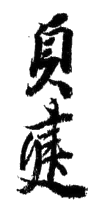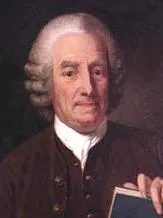生年: 1860年
名前: アントン・チェーホフ
職業: 小説家、劇作家
没年: 1904年
年 アントン・チェーホフ小説家劇作家 年
年ロシアの豊かな自然に囲まれたウゴリチ村で生まれたアントン・チェーホフは後に文学界の巨星として知られるようになる彼の家族は貧しい商人であり幼少期から困難な状況を経験しただがそれが彼の創作活動に対する情熱をかき立てることとなり皮肉なことにこの苦悩が彼を独自の視点を持つ作家へと導いたのである
青年時代チェーホフは医療に興味を持ち医学を学ぶためモスクワ大学に入学したしかしそれにもかかわらず小説や短編を書くことへの情熱は消えることがなかったおそらく彼の内なる葛藤はこの二つの世界医学と文学との間で揺れ動いていたからだろうこの時期多くの短編小説を書き始めその中には人間関係や社会的問題への鋭い洞察が見られる
年代には特に桜の園や三人姉妹といった戯曲によって一躍名声を博すこれらの作品では人の日常生活や感情が描写されているだけでなく無常さや人生そのものへの深い考察も含まれていたしかしその成功にも関わらずチェーホフは自己批判的だったと言われている私には文才などないとしばしば口にしていたという
皮肉なことに彼は年自身が長年苦しんできた結核によって死去するまで生涯医師としても活動していたそれゆえ多くのファンや批評家たちは病気という運命から逃れるためにも書き続けたと考えているおそらくその執筆活動こそが自身の存在意義を見出す唯一無二の手段だったからだろう
今日でもチェーホフ作品には普遍的なテーマがありますそれは愛人間関係孤独です現代社会でもこれらについて多く語られており桜の園は舞台上で今なお演じられているその影響力はいまだ衰えることなく新しい世代へ受け継がれているそしてその遺産として残された言葉は人の日常生活にも密接につながっているようだ
また一部ではチェーホフ効果という表現まで生まれその作品内で何気なく登場するアイテムやセリフが後重要な意味合いを持つという技法も注目されているそれゆえ多くの場合そのストーリー展開には観客や読者自身も引き込まれざるを得ないこの点について議論するファンも多くあれこそ真実だと語る人も少なくない
アントン・チェーホフはいわば自己表現によって人生そのものとの闘争へ挑んだ人物と言えるその成果として生み出された作品群にはただ感動させるだけではなく人の日常生活への深い洞察まで含まれており多大なる影響力を持ち続けているそして今なお多様性あふれる解釈と分析が行われ続けておりそれぞれ異なる視点から光輝いて見えるまた数世代先へ受け継ぐべきメッセージも秘めていると言えるでしょう